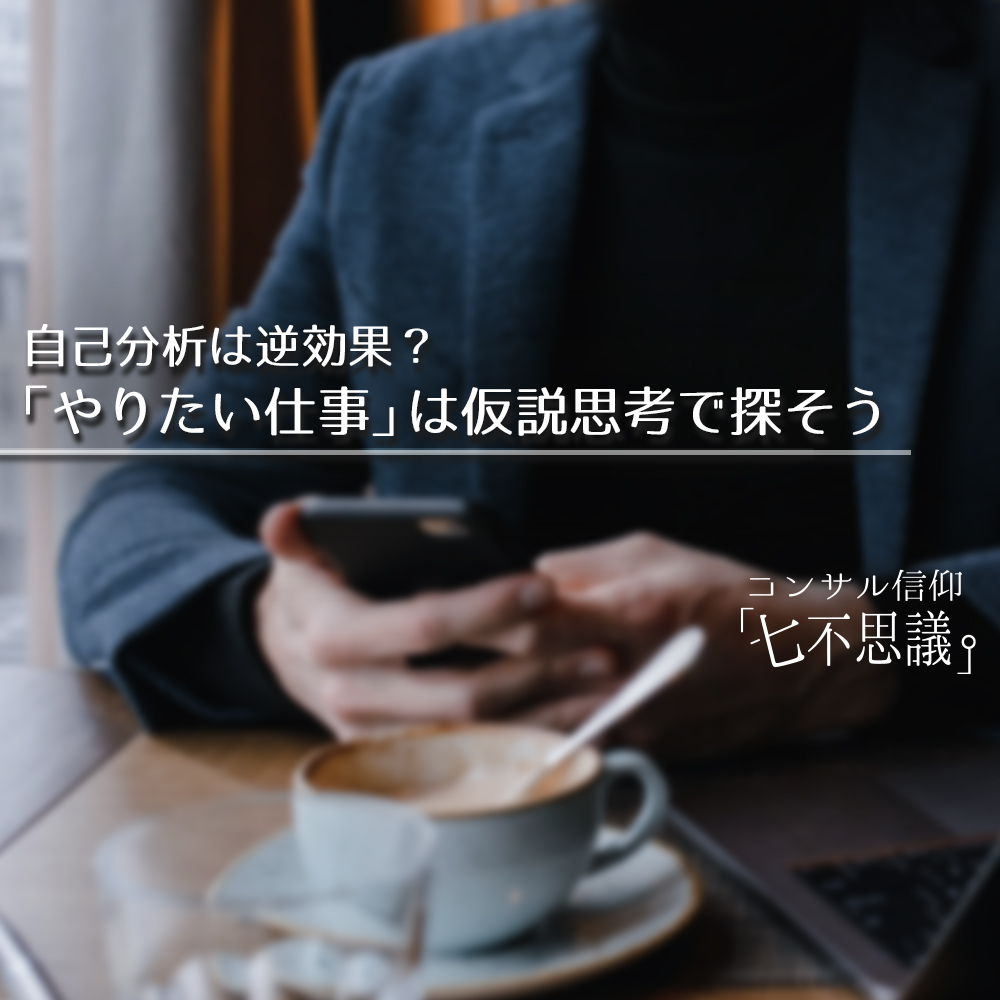転職というのは、その人のキャリア観が色濃く出る。特にそのキャリアチェンジが異色であればあるほど、「変わった人」と思われるかもしれない。
でも僕は「変わった人」というのは褒め言葉だと思うと同時に、こう思う。「もしかして自分の想像力が足りないだけで、その人の話をよくよく聞けば、何も変わったことはないのでは?」と。そう、きっとこの人だって。
東京・高円寺にある創業 昭和8年の老舗銭湯・小杉湯で働くガースー(菅原理之)さんの前職は、外資系広告代理店だ。「外資系広告代理店を退職し、銭湯で働きます!」というnoteを書き、異色のキャリアはメディアでも取り上げられたことがあるが、「変わっている」で終わらせるにはもったいない何かが、そこにはあるような気がした。
銭湯という場も、何やら物語のにおいがする。浮き立つ足は高円寺に向かっていた。
特集「あなたのキャリアに一目惚れしました。」
本特集では、ワンキャリ編集部が「一目惚れ」したキャリアの持ち主にお話を伺います。就活に直接関係ない話も多いです。いつか、あなたがキャリアを決めるときの一助となることを願って、お届けしたいと思います。
今回の惚れられた人:ガースー(菅原理之)さん

大学時代にNPO法人を立ち上げ、東京と山口の2拠点生活に。2005年にITベンチャーに転職し、2007年から外資系広告代理店に勤務。12年ほど広告業界で働き、2018年に独立。株式会社SUNDAY FUNDAYを設立し、「家業を事業へ!」をモットーに支援活動をする「Graft Producer」としての活動を開始。2019年9月から、創業 昭和8年の老舗銭湯・小杉湯にCSO(Chief Story teller)として参画し、この先100年と続く銭湯を目指している。
今回の惚れたインタビュアー:吉川翔大(編集者)
東京大学卒業後、2011年に新卒で中日新聞社に入社。長野、静岡、三重の3県で記者として働く。地方のユニークな人々や中小企業を取材する中で「楽しく働いている人の話を聞きたいし、もっとそんな人が増えてほしい」と感じ、2019年にワンキャリアに入社。1987年、京都市生まれ。
<目次>
●朝オフィスに行ったら、会社が倒産手続きに入っていた
●学生起業で東京と山口の2拠点生活に
●モヤモヤしない世界を作り、そこで生きようとする人たちに出会った
●冒険は戦略的に。だけど、緩いのは嫌だった
●好きなお店がなくなる寂しさと、足元にある幸せ
●最終的には、皆同じ何かに戻っていく
朝オフィスに行ったら、会社が倒産手続きに入っていた
──今日の取材は、菅原さんのnote「外資系広告代理店を退職し、銭湯で働きます!」を読んで、お願いしました。
菅原:noteは「広告代理店から銭湯に行った」と見せ方をしたらギャップが出るだろうと思い、そこを中心に書きました。でも、代理店に入った経緯も異色だったのかなと思います。
──その前はITベンチャーで働いていたんですよね。どうして広告代理店に転職したのでしょうか。
菅原:そのITベンチャーに民事再生法が適用されたんです。どうやら、社長が謎のお金の使い方をしていたらしく(笑)。「会社がヤバいんじゃないか」といううわさは出ていたのですが、朝オフィスにいると黒いスーツを着た人たちが段ボールを持って入ってきて「皆さん、手を触れないでください。作業を止めてください」と言われました。
──そんなことが……。まるでドラマのワンシーンですね。
菅原:「今日納品しないといけないんですけど」と僕が言ったら、「納品よりも現場保全の方が、優先度が高いので」と言われましたね。
一方でちょうどその頃、僕も広告代理店への転職を検討していました。当時、大手企業のWEBサイト構築やコンサルティングをしていて、ブランディングが課題になることが多く、もう少し広告の醍醐味(だいごみ)を感じてみたいという思いがあったんです。民事再生法の適用から3カ月後くらいに転職できました。
──ある意味タイミングが良かったのですね。
菅原:そうですね。結果的に、ビーコンコミュニケーションズという外資系の広告代理店に転職しました。たぶん普通に面接をしていたら入れなかったのですが、最後に「何か言いたいことがありますか?」と言われましたので、プロレスラー志望だったことを話しました。
──プロレスラー志望だったんですか?
菅原:僕は小さい頃プロレスラーになりたくて、中学生のときにプロテストの申請を出しています。新日本プロレスに入りたくて、野毛の新日の道場に行ったこともあります。そのことを話したら「面白いから採用」と言われました。後日、面接してくれた先輩に「あの話がなかったら採用していなかった」と言われました。何でもやっておいた方がいいし、何でも言っておいたほうがいいんだなと思いました。
学生起業で東京と山口の2拠点生活に
 ──そもそも、就活のときはどんな会社を受けていたのですか?
──そもそも、就活のときはどんな会社を受けていたのですか?
菅原:僕、就活はしていないんですよ。大学を中退して、NPO法人で働きました。
──そうだったんですか。どういうきっかけで働き始めたのですか?
菅原:僕が通っていた大学でボランティア論という授業があり、その講師の方が「ボランティアというものは無償で何かをやることではなく、自分から志願して何かをしてやるという意味だ」と話していて、いろいろな起業支援もやっていたんです。その支援を受けて僕も起業したのが始まりです。たぶん20歳頃でしょうか。
──どんな会社だったんですか?
菅原:コミュニティTVという名前のNPO法人で、映像を使った地方活性化に取り組んでいました。ちょうどパソコンで映像編集ができるようになった頃で「誰もが簡単に映像を使って自己発信ができる世の中になるのではないか。小さな声がいっぱい世の中に出ていくようなことをやれると、地方での情報格差がなくなっていくのではないか」と思いました。
具体的には山口県で番組制作をしたり、ホームページを作って映像や写真を発信する授業を小学校で開いたりしました。東京と山口の2拠点生活みたいになりましたね。
──確かに、学業との両立は難しそうです。「とりあえず卒業しておこう」とは思わなかったんすか。
菅原:その頃は大学で勉強するよりも社会に出た方が、学びが多いと思っていました。圧倒的に刺激は大きかったですし、同年代の学生よりも上の年代の大人の中にまざってやることのほうが面白かったので、1年生の後半くらいからほぼ大学は行っていません。若気の至りみたいなところもありましたね(笑)。
でもテストだけは受けていて、3年生までは上がっているんです。ですが、体育はさすがに行かないと単位が取れなくて「これは無理だ」と思って3年生の後半で中退しました。
──じゃあ地方でお仕事をした後に、ITベンチャーに転職したのですね。NPOの仕事は何歳くらいまでしていたのですか?
菅原: 25歳くらいだったかな。インターネット黎明期(れいめいき)の中で、パソコン教室からWEBサイトの製作、映像編集、メルマガ制作までひととおり、いろいろなことをやりました。その中で「もう少し華やかな仕事をしたいな」と思いました。20歳くらいで社会に出てから3~4年やってみて、視野が広がり、もっと別の世界もあることが見えたのでしょうね。いろいろな人がブログで発信し始めた時代で、他の世界も見えるようになったことも大きかったと思います。
当時の僕のキャリアはテクノロジーと地方という2つのキーワードがあったと思いますが、テクノロジーがこれからの時代を開くだろうと思えたので、そちらに走った感じです。
モヤモヤしない世界を作り、そこで生きようとする人たちに出会った
──さまざまな会社でキャリアを積んでこられた中でも、結果的に広告業界がキャリアの中では一番長いのでしょうか?
菅原:はい。広告業界には12年くらいいました。最初に入ったビーコンコミュニケーションズで10年、次のジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパンで1年半くらいやっていました。
──印象に残っているお仕事はありますか?
菅原:ビーコンコミュニケーションズに僕はデジタルプロデューサーという肩書で入って、最初に担当したのがナイキさんでした。入って2カ月くらいのときにランニングの計測ができる機器のキャンペーンがあって「君1人でチャレンジ的にやってみたらどう?」と、当時の上司から言われました。
そのときに話を持ちかけたのが、Webメディア「オモコロ」の編集長だったシモダテツヤくんです。
・日本で初めて「おふざけ」を仕事にした男に、『遊び』の感覚はなかった。シモダテツヤが語る、『やりたいことを引き寄せる』法則
当時の状況として、お金がないから面白くするには知恵とアイデアでどうにかするしかなく、オモコロの皆に相談して「面白くて走るモチベーションにもなる企画を作ろう」という話になりました。それで「変な体勢で走ってみた」みたいな記事を作りました。
1カ月くらい皆でずっと話しながら遊びながら、走っているところを撮影しました。そこでつながった人たちとの関係は、今もめちゃくちゃあります。人と一緒に仕事をして友だちになれる楽しさ、友だちと仕事をする楽しさが分かったんですよね。
──誰と一緒にするかは、仕事においても大事ですよね。
菅原:印象に残っている仕事はもう1つあって、デジタルアカウントチームを作ったことです。デジタル領域での強みを作り、関わる人たちをハッピーにしたいと、社長に直接話を持っていき、最終的には十数名いるチームに育ちました。年齢、国籍、働いてきた背景もバラバラの人たちを、マネジメントしたことは大きな経験です。自分の意見をちゃんと持って話していくと、それが実際に形にできたこともよかったですね。
──聞いていると、広告代理店のお仕事もやりがいがありそうです。
菅原:そうですね。やりがいはありました。広告代理店で働いていたときに持ったのは「レベルアップ」していく感覚です。ドラクエに例えるなら、1つ上の職業に変わるというのは役職が1つ上になることだし、レベルアップしてステータスが上がるような感覚もありました。
特に数字で見える給料という意味では、分かりやすいレベルアップ感はあったかな。チームができて、そのチームの人数が増え、担当しているクライアントの数も増えるというのも、自分の中ではレベルアップ感がありました。
──でも、退職されたんですよね。そのレベルアップが楽しくないとか、幸せじゃないとかを感じるタイミングがあったんですか?
菅原:日々の中の違和感かな。大人の事情でチームメンバーが信じていたものが止まってしまうとか、「この広告を見る人たちのために本当になるものなのか?」と考えるとか。そういうものがだんだん積み重なっていき、「このモヤモヤは何だろう」とは思っていました。
──モヤモヤを割り切ることもできたと思うんですが、それを放置できなかったのはどうしてでしょうか?
菅原:モヤモヤしない世界を作ってそこで生きようとしている人たちを見たことが大きいです。先程のシモダ君もそうだし、オモコロで一緒に仕事をした編集者の徳谷柿次郎君もそうです。
大人としてモヤモヤを飲み込んで仕事をすることも1つの道だったと思うし、それも正解だと思います。でも僕の場合はそうではない世界をやっている人たちが見えて、自分はそちらに行きたいと思ったんです。
仕事って楽しいだけではなく苦しいこともめちゃくちゃあります。でも同じ苦しさでもそちらのほうが気持ちよく生きていけそうだと思いました。
冒険は戦略的に。だけど、緩いのは嫌だった

──ゲームとしてのレベルアップという意味では、会社を辞めるということは、そのレベルを一度リセットすることにもつながります。その怖さはありましたか?
菅原:正直、それはありました。
──怖さとは、どう向き合ったんですか?
菅原:すごく現実的に考えました。お金的な計算から、自分の年齢的にどういう仕事ができるのかまで、現実的にどうなるのかを、できるだけ目に見える形に落とし込もうとしました。
たぶん漠然とした不安だけを持っているから、余計に不安になるんです。分からないものを分からないままにしておくことが、一番の不安の原因です。何か足りないということが見えたとしても、課題が見える限りは解決できると思っています。
僕は冒険している部分もあるけれど、考えなしにやっているわけではなく、戦略的な冒険をしているのだと思います。
──次のキャリアの選択肢はたくさんあったと思うんですが、小杉湯に決めた理由は何だったんですか?
菅原:一番は3代目の平松佑介と働きたいと思えたというのが理由です。また、小杉湯には代理店にいるときから1年間くらい個人的に関わってはいました。キャリアを考えるに当たって改めて小杉湯のことを考えたとき、小さい頃に風呂無しの家に住んで銭湯に通っていたことが思い出されて。銭湯には公衆衛生のためのお風呂という機能はもちろん、それ以外に地域コミュニティーを育み、人との接点を作るみたいな、現代におけるいろいろ必要な機能を持っています。
そこが自分の最初のキャリアにあった地方の課題に向き合うともつながって、すごく面白いと思えました。
──「戦略的な冒険」という意味では、小杉湯に緩く関わり続けることもできたと思います。例えば他に本業を持ち、副業としてでやることもできたような気がします。
菅原:外からそれっぽいことを言って自分は手を動かさずみたいな関わり方は、嫌いなんです。複数の企業に緩く関わり、月に十万くらいもらえる収入源が何本もある、みたいなのは好きになれなくて。特に家業の現場に入ってみて、ある程度二人三脚で歩かないと物事は達成できないと思うようになりました。
この先100年続くような銭湯にしていくためには、外の人として何か会話をすることではなく、中にも足を突っ込みながら外と中をつなぐ人にならないといけません。
──当事者として、本気で仕事がしたかった、と。
菅原:小杉湯のトップは3代目の平松なのですが、外から話しているだけだと、お客さんとコンサルの関係にしかなり得ないと思います。その人に対して本気で怒ることはできないと思うんです。同じ共同体の中にいる仲間として意見をちゃんと言うことが、少なくとも僕はできないです。
──中の人なら、耳の痛いことを言わないといけない場面もありそうです。
菅原:でもそれをやらないと。「いいですね、面白いですね」とだけ言っている人なんてあまり必要ないと思っています。

大事なことは、経営者を孤独にしないことです。経営者の孤独がなぜ起きるかというと、ある程度自分と同じ立場で向き合って意見を言ってくれる人がいなくなってしまうからです。社員に対して言えないこともあるだろうし、そもそも見る目線が違うから課題が共有されにくいこともあるだろうし。
完全に同じは無理だと思いますが、それくらいの気持ちで関わっていないと、孤独が解消できないのではないかという気がします。
──お互いに真剣だから、怒ったり怒られたりができる関係が生まれそうですね。
菅原:何ならアルバイトの人たちからも「もっとこうしたほうがいい」という意見が挙がってくるし、僕が怒られることもあります。
──そうなんですか? 小杉湯で働いている人たちの特徴なのでしょうか。
菅原:確かに主体的に小杉湯に関わってくれる人は多いですね。小杉湯の人でもメディアに出てくるのは、僕みたいな比較的目立つキャリアの人が中心ですが、銭湯は別にその人たちだけでできているわけではないです。
朝の掃除をするおばちゃん、開店準備をするアルバイトの人、実際に開店したらタオルを畳んだり掃除したりする番頭がいて、番台がいて、仕事が終わって1時45分。そこから深夜清掃をする人たちがいて、やっと3時から4時くらいにお店が終わってという感じです。役員、従業員、アルバイト、パートタイム合わせて今30人くらい関わって毎日の営業ができています。
そこってたぶん見えないじゃないですか。メディアに出ている情報だけだと、僕や経営者が「こんなことをやりました」「こんなアイデアでやりました」「こんな世界を作っています」と話しますが、それ以上に毎日現場で働いている人のおかげで清潔で気持ちよいお風呂ができているというのが小杉湯の根幹です。
好きなお店がなくなる寂しさと、足元にある幸せ
──小杉湯に移ってから、働くことへの価値観は変わりましたか?
菅原:広告代理店で働いていたときは毎日何か刺激があることが幸せだと思っていました。だけど小杉湯に入って、特別な刺激はないけれど何でもない一日も大切だと思えるようになりました。
以前は足元に目を向けられなかった気がします。お風呂が毎日普通にきれいであることは、実はいろいろな人の積み重ねでできているのですが、そういうことにはなかなか目を向けづらかった。華やかで目立つところに目がいっていたのが、当時の僕でした。
──広告は未来に向けて今はないものを作っていくお仕事が多いと思うので、余計に先に目線が向いていたのかもしれませんね。
菅原:そうかもしれません。他と違うこと、差別化が広告には必要で、変わったことを求めます。いろいろな経験を通じて新しい刺激をどんどん手に入れている感覚はあったのですが、追われている感覚もありました。駆け抜けてはいるけど、その一歩一歩に充実感があったかと問われると、疑問が残ります。
今は新しい刺激が強いものばかりではないけれど、1つ1つのことにしっかりと向き合えている。そういう感覚を持つことは増えました。小さなことかもしれませんが、お風呂に入ったお客さんの顔を見て「幸せそうに帰っていくな」と思う瞬間がとても大事に思えるんです。
──小杉湯ではどんな業務をされているんでしょうか?
菅原:中長期的な目線で小杉湯の事業に取り組むことが多いです。例えば、新商品開発。新型コロナウイルスの感染拡大で、その場に人が集まりにくい状況になっているので、別のビジネスモデルを持っておかないと、銭湯自体が続けられなくなる可能性があります。かといって銭湯から完全に足を離したものをやっても意味がないと思うので、その中で銭湯に関連する新しい商品開発をしています。
──コロナの影響は大きいですよね。
菅原:そうですね。他にも、家業を事業にしていくという、事業としてこの先もやっていける基盤作りをやっています。人事労務、経理面も含めて計画を作っています。
例えば、過去の取り組みだと産休育休制度の整備です。なかなか世に出にくいものかもしれませんが、働いてもらう上ではとても大事な基盤です。
──外に向けた活動だけでなく、内側も整えている、と。
菅原:結局は全て小杉湯のブランディングにつながると思っています。世に広告として出ているメッセージだけではなく、カルチャーの在り方や姿勢も含めてブランドは作られます。社員やパートタイム従業員も含めた働き方など、言行一致をしっかりさせていくことこそブランディングだと思います。だから、そこまで手を出してやっています。
──……聞いていると、めちゃめちゃ忙しそうです。
菅原:正直、前職よりも忙しくはなりましたね(笑)。
──それから、「長く続く」ということも大切にしていると思いました。そこを大事にしたい理由はなぜでしょうか?
菅原:自分の好きだったお店がなくなってしまうとか、すごくいいものづくりやサービスをしているのに経営的に立ち行かなくてなくなってしまうこととかが、寂しいんです。自分が好きなものが自分の周りにあると、それだけで生活は楽しくなるじゃないですか。
自分が応援したい人やサービス、組織が続くように、僕自身が持っている経験や力でできることをしようと思ってやっています。
小杉湯でやっていることの1つに、地方の生産者さんと高円寺をつなぐ「もったいない風呂」というプロジェクトがあります。例えば、商品として出荷できないミカンがあったら、お風呂に入れてミカン風呂にする。番台前でその農家さんの生産品を販売もすれば、「ミカン風呂、気持ちよかったな」と思ってもらえったお客さんに買ってもらえるかもしれない。
農家さんは自分たちのことを知ってもらえ、実際に買ってもらうことでも応援もしてもらえる。かつ、高円寺の人たちには、生活の中に新しい価値をお届けできるのではないかと思います。僕自身も地方を回ったので、地方の作り手さんをつないでいきたいですね。
──身近な幸せを大切にすることが菅原さんにとっては、とても重要なことなんですね。
菅原:歳を取ったんでしょうね(笑)。
20代の頃は常に新しいものやサービスが生まれることに目がいきましたけど、「今自分が楽しんでいるものがなくなってしまう」ということは、あまり考えませんでした。でも年齢を重ねるにつれ、自分が好きだったお店が、少し行かない間に閉店しているということもあって。35歳を過ぎた頃から「一生あるものはないんだな」と自覚したのだと思います。
最終的には、皆同じ何かに戻っていく
──改めてご自身のキャリアをどう思いますか?
菅原:自分の好奇心に正直に生きてきた気はします。「大学を卒業して就職することが当たり前」と思っていたけれど、在学中に起業して中退したときに、「この日本においては、よほどじゃない限り食えなくて死ぬことはないんだ」と思えたのが大きいですね。最終的にアルバイトをすれば生きていけるし。それよりは動かなかったことを後悔するほうが僕は怖いと思っています。
──でも、「アルバイトをすれば生きていける」という事実を理解しても実行に移すのは難しいですよね。僕はその理由って、人と比べるからではないかと思っています。「あいつは社会で活躍しているのに、自分はアルバイト生活」という状況って、想像すると自分がみじめに思えてしまいそうで。菅原さんは人と比べることはなかったのですか。
菅原:めちゃくちゃありましたよ。ずっと人と比べて生きてきたと思います。でもそれが少なくなってきたのは……、なぜでしょう、これもおじさんになったからかな。最終的には比べてもしょうがないと、比べたところに幸せがないと、だんだん思えてきたんでしょうね。最終的には皆同じになっていくなと思います。
──結局どんな人も老いるし。
菅原:自分の息子とおじいちゃんおばあちゃんが、似たような行動をしているのを見ると、人は最終的に何かに戻っていくのではないかと思いますね。
──銭湯って、そういう瞬間が見える場所かもしれませんね。お風呂に入って気持ちよさそうにしている瞬間って、老若男女に訪れるものですし。
菅原:今も比べてしまうことはありますけれどね。でもそれが少なくなってきたかな。
*
取材を終えた後、小杉湯の皆さんのご好意でお風呂に入らせてもらった。子どもからお年寄りまでが気持ちよさそうに湯船に浸(つ)かる姿を見て、ガースーさんのいう「特別な刺激はないけれど何でもない一日」の一幕が、そこにあった。
でも、何でもない一日も、誰かの仕事で成り立っている。ガースーさんの話を聞いた今、はっきり実感できた。

<ガースーさんが好きなキャリアの人>
「最近は会った大体の人に対して『この人の生き方すごくいい』と思うことが多いです」と語る菅原さん。その中で「特に」と感じた人を挙げてもらった。
まず挙がったのが、記事にも出てきたシモダテツヤさんや徳谷柿次郎さん、長野県富士見町でシェアオフィス「富士見森のオフィス」を運営する津田賀央さん。いわゆる「モヤモヤしない世界」を自分たちで作ってきた人たちだ。
もう1人挙がったのが、写真家の幡野広志さん。多発性骨髄腫という難病を患い、余命宣告を受けた状態で活動を続ける幡野さんは、小杉湯のWEBサイトの写真も撮影した。「よくこんなに達観した視点が持てるなと思うことがすごく多い。自分も大事なことをちゃんと見つめないと、と思います」
【撮影:百瀬浩三郎】
【特集:あなたのキャリアに一目惚れしました。】
・「生きもの」感覚を大事に、「いい大人」とめぐり会い、「一生考えましょうよ」──中村桂子さん(前編)
・一生懸命に生きている「いい大人」と出会う。そして、一生考えることが、好きになる。──中村桂子さん(後編)
・結婚・出産で就活断念。「予期せぬ出来事」は、キャリアを強くするきっかけになる──太田彩子さん
・「役に立たない」は未来へのバトン。だから私はキリンの解剖が続けられている──郡司芽久さん
・「あのね、ぼくは、そういう特別なきっかけで、動いたことがないんですよ」──伊藤守さん(前編)
・「死んじゃった人を信じるのは、簡単。生きている人を信じるのが、難しい」──伊藤守さん(後編)
・湯上がりの幸せを、ずっとこの先も。僕らの未来を広告でなく銭湯で守りたかった【小杉湯・ガースーさん】
・「留年して、建設省への就職がおじゃんに。それで大学院のあと、野村総研へ入るんです」 山形浩生さん(前編)
・「誰も何も言わない世界と、読まれなくても誰かが何か言う世界は、多分違う」──山形浩生さん(後編)
・「なんで急に落ちこぼれになったんだろう?」苦しかった就職活動と可能性が広がった20代──今井麻希子さん(前編) ・「見つかっちゃった!出会っちゃった!」やりたいこととの衝撃的な出会い──今井麻希子さん(後編)



















.jpg)