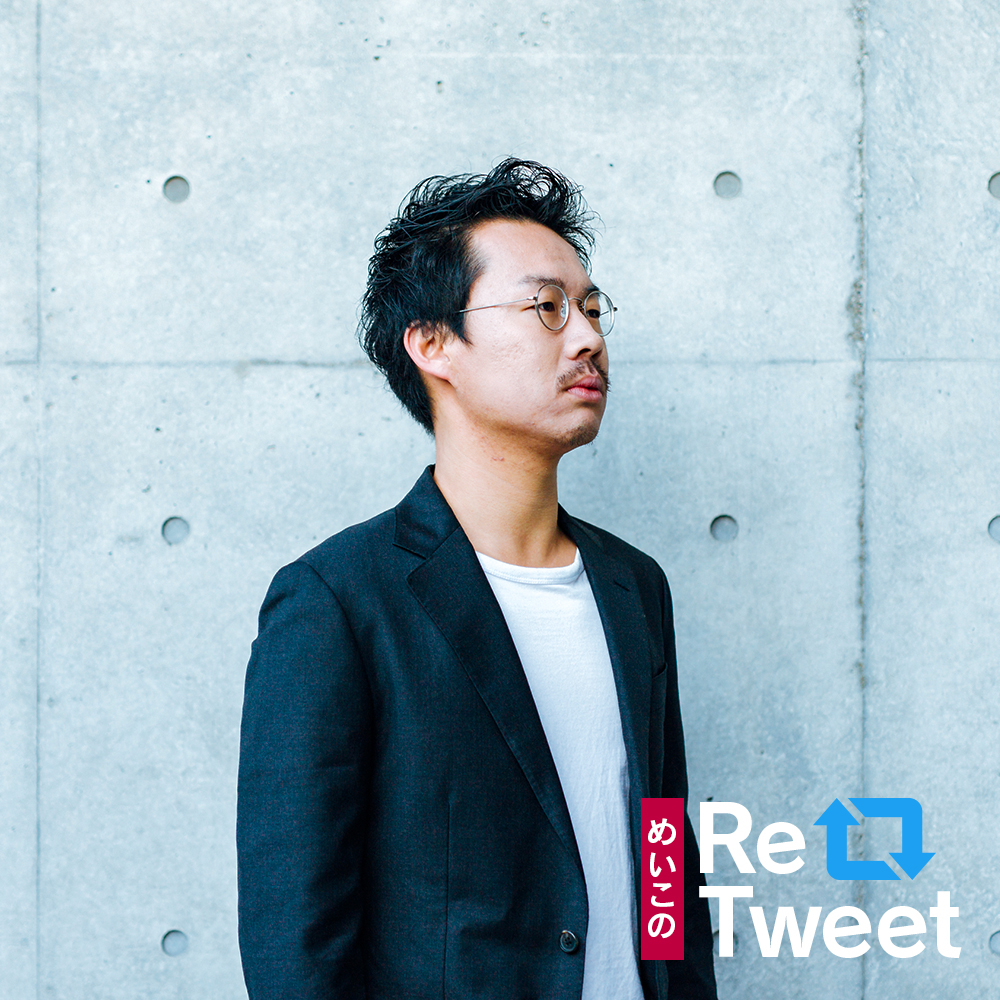新入社員として入社して数カ月たった2010年初夏、宮崎駿さんのアトリエへ向かった。私は手に、発売されたばかりのiPadを持っていた。
アトリエのカウンターで、宮崎さんの隣に座る。いそいそとiPadを見せる私に、宮崎さんは問うた。「それで、何ができるんですか?」。
私は、YouTubeのアプリをタッチし、「たとえば、こんな風に、動画が見られるんですよ」と伝えた。
すると、間髪を入れずに、宮崎さんは言った。「あなたの言う『動画』とは、どういう意味ですか?」
「え?」。私には質問の意味が分からず、会話は止まり、沈黙が訪れた。
宮崎さんにとっての「動画」とは、「動画マン(アニメーションにおいて、原画と原画の間の連続する動きを作画するスタッフ)」という意味の「動画」だった。アニメーション監督である宮崎さんの「動画」と、YouTubeを見続けたことで大学を留年した私の「動画」とでは、言葉の意味が違ったのだ。
相手と自分の言葉の定義の差異に気づくことは、コミュニケーションにおいて、とても重要だ。年長者との会話を通じて、自分がいかに言葉に無頓着に生きてきたか、気付かされた。
社会に出て10年がたつ。色んな痛い目にもあってきたが、その多くはコミュニケーションの失敗だった。そうした数々の試行錯誤を経て、私はコミュニケーションに強い関心を向けるようになった。
だから、人間関係やコミュニケーション、そして組織改革をテーマにする「伊藤守さんの著作」にも出会えた。そして、今回、伊藤守さんに取材をした。
特集「あなたのキャリアに一目惚れしました。」
本特集では、ワンキャリ編集部が「一目惚れ」したキャリアの持ち主にお話を伺います。就活に直接関係ない話も多いです。いつか、あなたがキャリアを決めるときの一助となることを願って、お届けしたいと思います。
今回の惚れられた人:伊藤守さん(コーチ、経営者)
 1951年、山形県生まれ。日本大学大学院 総合社会情報研究科 修士課程 修了。1975年に日本大学商学部卒業後、商社に勤務したのち、26歳のときに独立をして貿易商社を起業。1980年からはコミュニケーションに関する研修・教育事業および研究を始める。1984年、株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワンを創業。1996年に「coach」という言葉と出会い、1997年に株式会社コーチ・トゥエンティワンを設立して、日本初のコーチングプログラムの提供を開始。2001年、エグゼクティブ・コーチング・ファームとして株式会社コーチ・エィを設立。現在は、コーチ・エィの取締役、ディスカヴァー・トゥエンティワンの代表取締役会長を務める。人と人との関係やコミュニケーション、組織改革をテーマに、経営者を対象としたエグゼクティブ・コーチングに従事するほか、地方公共団体、教育機関、経営者協会などにおける講演活動や執筆活動も行う。主な著書に、『こころの対話』(講談社、1995年)、『もしもウサギにコーチがいたら―「視点」を変える53の方法』(大和書房、2002年)、『コーチング・マネジメント―人と組織のハイパフォーマンスをつくる』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2002年)、『小さなチームは組織を変える―ネイティブ・コーチ10の法則』(講談社、2004年)、『3分間コーチ ひとりでも部下のいる人のための世界一シンプルなマネジメント術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2008年)など、多数。
1951年、山形県生まれ。日本大学大学院 総合社会情報研究科 修士課程 修了。1975年に日本大学商学部卒業後、商社に勤務したのち、26歳のときに独立をして貿易商社を起業。1980年からはコミュニケーションに関する研修・教育事業および研究を始める。1984年、株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワンを創業。1996年に「coach」という言葉と出会い、1997年に株式会社コーチ・トゥエンティワンを設立して、日本初のコーチングプログラムの提供を開始。2001年、エグゼクティブ・コーチング・ファームとして株式会社コーチ・エィを設立。現在は、コーチ・エィの取締役、ディスカヴァー・トゥエンティワンの代表取締役会長を務める。人と人との関係やコミュニケーション、組織改革をテーマに、経営者を対象としたエグゼクティブ・コーチングに従事するほか、地方公共団体、教育機関、経営者協会などにおける講演活動や執筆活動も行う。主な著書に、『こころの対話』(講談社、1995年)、『もしもウサギにコーチがいたら―「視点」を変える53の方法』(大和書房、2002年)、『コーチング・マネジメント―人と組織のハイパフォーマンスをつくる』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2002年)、『小さなチームは組織を変える―ネイティブ・コーチ10の法則』(講談社、2004年)、『3分間コーチ ひとりでも部下のいる人のための世界一シンプルなマネジメント術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2008年)など、多数。
今回の惚れたインタビュアー:佐藤譲(コーチ、編集者)
1986年、福岡県生まれ。2005年、京都大学法学部に入学。2009年秋に大学卒業後、株式会社スタジオジブリへ入社。鈴木敏夫プロデューサーと同じ家に住みながら、編集者として働く。2015年、日本テレビ放送網株式会社に入社。実写映画・アニメーション映画のプロデューサーを務めたのち、2018年に独立。ゲームベンチャーの立ち上げに関わったのち、現在は、『100年ドラえもん』の宣伝ディレクションや、スタジオジブリ最新作のアート本の制作を担当するほか、トラストコーチングスクール認定コーチとしてクリエイター向けにコーチングを行う。また、大学生向けのキャリア支援としてWividとワンキャリアに関わり、ワンキャリアでは本特集「あなたのキャリアに一目惚れしました。」の立ち上げから参加。最も繰り返し読んだ伊藤守さんの本は『こころの対話』(講談社、1995年)。
<前編 目次>
●「パーパス」を作る必要がなかった時代
●難しいことが、面白い。
●退屈の極み
●モヤモヤとの付き合い
●特別なきっかけで、動いたことがない。
伊藤さんは、「コーチング」を日本に導入した第一人者だ。自身もコーチとして活躍されてきた。コミュニケーションのプロであるコーチに取材をするのは、やっぱり緊張をする。
会うまでに、入念に準備をする。伊藤さんは1951年に生まれ、69年がたつ。伊藤さんに関する知りうる限りのことを調べ、想(おも)いをはせる。
すると、「あれ?」と、自分の思い込みに気づいた。
人間関係やコミュニケーションに関する本である『こころの対話』は1995年に出版された。一方、伊藤さんが「coach(コーチ)」という言葉と出会ったのは1996年だった。
私は勝手に、『こころの対話』を「コーチ」である伊藤守さんが書いた本だと思って読んでいたが、『こころの対話』は「コーチング」に出会う前の伊藤守さんが書いた本だったのだ。
伊藤守さんは、コーチングに出会う前から、コーチだったのではないか? もしもそうだとすれば、私は、「コーチ」になる以前の伊藤守さんのことをもっと知りたい。だから、取材では、40代前半までの伊藤守さんが大事にしたことを、伺おう。「伊藤守さんの前史」を、伺おう。
丹念に準備をして臨んだ。いくつかの仮説も持っていた。しかし、いずれの仮説も崩れることになる。
「パーパス」を作る必要がなかった時代
──伊藤守さんには、「経営者」の顔や、「コーチ」の顔をはじめ、さまざまな側面があります。今日の取材では、そうしたさまざまな顔、つまり、書籍を通じて私が出会った「伊藤守さん」以前の「伊藤守さん」に焦点を置いて、お話を伺いたいと思います。
伊藤守(以下、伊藤):ぼくに興味を持ってくださって、ありがとうございます。
──私は1986年生まれの33歳で、記事を読む読者の多くは20〜30代です。自分が生まれる以前の時代のことを想像することは、とても難しいことです。そこでまずは、伊藤さんが生きた時代のことを、伊藤さんの視点で教えていただけないでしょうか?
伊藤:ぼくは1951年生まれで、この年に初めて、民間航空会社として日本航空が設立されました。それまで日本は、飛行機を飛ばしちゃいけませんでした。作ってもいけなかったんです。
最近、先行きが分からない時代に、多くの企業・経営者が存在価値を問い直す表現として、「ミッション」や「ビジョン」ではなく、「パーパス」という言葉が使われます。社会的な存在意義や目的のことです。
ぼくの父たちの時代は、「パーパス」なんて別に作らなくて良かったんです。なぜなら、戦後、「復興していこう」というパーパスがみんなに共有されていたので。「みんなで、国を復興していく。もう一度、経済を安定させる」って。
──戦後は「社会建設」という言葉や感覚があったと、1948年生まれの作家・橋本治さんの本で読んだことがあります。みんなが貧しく、みんなが明るい未来を描いていた時代があった、と。
伊藤:1970年の大阪万博を超えるあたりまでは、「国を復興していこう」という勢いで日本は来たと思います。たぶん、70年代のオイルショック辺りから、少し変わり出すんじゃないですかね。バブルの予兆が見えてくる。そして、価値の多様化も、始まってくるんです。
ぼくにとって、オイルショックって大きな出来事で。「この世界に、ミドルイーストというものがあるんだ。それが経済を動かしているんだ」って知りました。ものを作ったり消費をしたりするのではなく、「エネルギー」というものを前提にする必要があるんだって。考え方が根底から変わりましたよね。
──なるほど……いや、「なるほど」と言ってしまいましたが、分かっていないです。というか、分かっていないことも、分かっていないです。私は86年生まれだからか、グローバル化が進み、世界のさまざまな地域が互いに影響し合っていることや、「エネルギー」も前提になりすぎていて……感覚的にどうしても分かりません。
伊藤:86年生まれも、96年生まれも、2006年生まれも、もちろん、みんなそれぞれ違うんでしょうけどね。
66年に五木寛之さんが『蒼ざめた馬を見よ』で、67年に野坂昭如さんが『火垂るの墓』『アメリカひじき』で、直木賞を受賞します。69年には庄司薫さんが『赤頭巾ちゃん気をつけて』で芥川(あくたがわ)賞を受賞。寺山修司さんが劇団「天井桟敷」を結成したのが67年です。そういう時代です。
柴田翔さんの『されどわれらが日々』は64年の芥川賞受賞作品でありベストセラーですが、あれは、六全協(日本共産党第6回全国協議会)に影響された学生のお話ですから。今の若い人たちは、きっと山村工作隊なんて知らないでしょうね。ぼくは活動家ではありませんでしたけれど、そういうものがコモンセンス(常識)だった時代ですよね。

──スタジオジブリの鈴木敏夫さんが1948年生まれの方で、いろんな話をしてきたので、少しだけですが、私はイメージが湧きます。
伊藤:1951年生まれのぼくは、ベビーブーマーの一番最後のほう、って感じですよね。
ぼくの父は、東京生まれ東京育ちの人で、何代も続いた鋳物屋さんだったんです。戦争が終わって、山形県に工場を誘致して、そちらに移ってから、ぼくは生まれました。
父は東京の人だし、母は満州からの引き揚げですから、二人とも山形弁を話さなくて、ぼくは山形弁を最後までしゃべらなかったですね。
──私は父がサラリーマンで転勤族だったので、幼い頃に九州から長野に移りました。方言を話さないと、かなり浮きますよね。私は幼稚園児の頃に、からかわれたのを覚えています。
伊藤:母はのちに山形弁を少し話すようになりましたけれど、ぼくは器用じゃないので、基本的に山形弁を話さないし、あんまり馴染(なじ)めなかったですよね。幼稚園にも行きませんでしたし。
大学入学のときに山形を出て、東京へ行きます。父の会社は東京に本社があって、父のお兄さんが東京にいましたから、子どもの頃からよくその家に行っていました。だから、東京へ行くことにも、特に違和感はなかったですね。
──伊藤さんが入学される日本大学では、1968年から学生運動(日大闘争)が巻き起こっています。
伊藤:ぼくが入学する70年には、もうかなり下火でしたよね。高校生のときだったので、東大闘争もテレビで見ていましたよ。高校のクラスメートと、よく話題にしていました。
その頃って、いろんなものが出ている印象があります。J.D.サリンジャーの小説『ライ麦畑でつかまえて』が翻訳されたのは60年代前半ですし、ビートルズが出てきたのもその頃。ぼくは中学生でした。ジャン=ポール・サルトルが来日したのは、66年9月です。友人と実存主義について話していましたよね。
ジャズも全盛でした。ジョン・コルトレーンも、マイルス・デイビスも、セロニアス・モンクも。大学1年生の頃に、チック・コリアが出てきたかな。一方では、ボブ・ディランがいて、ジョーン・バエズがいて、エルヴィス・プレスリーのラスベガス公演は69年夏。サイモン&ガーファンクルや、シュープリームスも出てくる。どんどん音楽が変わっていきました。
外の世界が、どんどん移り変わっていく中に、ぼくはいたんです。
──時代がダイナミックに動いている様子が垣間見えます。
伊藤:ぼくは高校生の頃から、ギターを弾いたり、ピアノを弾いたりしていました。大学生のときは、新宿や赤坂のお店で、ギターやピアノのアルバイトをしていました。新入社員でもらう収入よりもずっと多かったので、経済的にはあまり困らなかったです。
ピアノを弾いたり、歌を歌ったりして、「これで、生きていこうかな」と思っていた時代もあるんですよ。初任給の平均が3万円くらいの時代に、ぼくは30万円くらいもらっていましたから。でも、そのうち、カラオケが生まれて、駄目になるんですよね。結局、セミプロの歌を聴いているよりは、みんな自分で歌いたいんですよね。
「そういう時代が来たんだ」と思って、さっさと足を洗っちゃった、って感じでした。

難しいことが、面白い。
──20歳前後の伊藤守さんは、どんな大学生活を送ったのでしょう?
伊藤:大学へ通って、いろんな人と関わるようになると、優秀な先輩がいるんですよね。当時の日大は、どこかの学校を辞めさせられた先輩たちが来ていて、すごく優秀だった。
先輩の家に行くと、部屋中に本があって。「ぼくも3年くらいたったら、追い越してやる」って先輩に言ったら、「おまえは永久に追い越せないよ。だって、俺はずっと読み続けるから」なんて言われて。大人げない人だなぁ、なんて思ったけれど(笑)。
先輩たちから「まずは、岩波新書100冊くらい読んでから、お話ししようね」なんて言われました。「スタンダールの『恋愛論』についてしゃべってみて」という風に、よく試されましたね。吉本隆明さんの本も読まされました。
──そういうやり取りは、伊藤さんは楽しかったんですか?
伊藤:ぼくは、そりゃ面白いですよ。
だって、小学校から一度もお勉強をしたことがないんですよ? 机に向かって30分以上、勉強ってしたことがなかったんですよね。脳にすごくゆとりがあるわけ。何も詰め込んでいないんですから。だから、スポンジ状態で、いろいろ入ってくるんです。面白くって、面白くって。
それに、興味あることしかやらないんだからさ。ぼくには、努力とか、頑張るとかって、辞書にないから。学ぶことが面白くて仕方なかった。
──ぼくは「難しい」ことって、ついつい「頑張る」とセットに考えてしまいますが。
伊藤:面白いことっていうのは、基本的には難しいんですよね。人生っていうのは、ある意味では、難解な問題をどんどん用意していくものでもある。
会社では何が厄介な問題になるかというと、たとえば、「社長と副社長が、半年間、口をきいていません」っていう会社で、「どうやって口をきかせるんだ?」というのが難しい問題だと思うんです。
あるいは、たとえば、1万円を友だちに貸したら「返してよ」って言えるけれど、10円だとなかなか言えない。もんもんとするんですよね。そして、「10円を貸したじゃない?」って気持ちを抱えつつ、友だちとしゃべるわけでしょう。「人間は大きなことに対応できるけれど、どうして、こういう小さいことに対応できないんだろう?」というのは、案外解決されていない問題だなってぼくは思うんですよね。
難しいことって、面白いんです。

退屈の極み
──大学生になって、スポンジが水を吸収するように、さまざまなことを吸収していく伊藤さんは、社会に出るにあたって、どんなことを考えていたんですか?
伊藤:就職する気も、何にもないんですよ。音楽でまあまあのお金をもらっていましたから。毎日が楽しいし、土日はちゃんとお休みがあるし。仕事は、夜に3〜4時間、やればいいわけですから。
でも、大学5年生の夏休み頃に、いよいよ退屈しちゃったんです。周囲は卒業をして就職をしたから、友だちがみんないなくなっちゃって。その頃は、毎晩仕事をして、昼間にプールサイドで身体を焼いていたんですけれど、「これはもうダメだなぁ」と思いました。「退屈だなぁ」って。
──ぼくも大学生のころ、YouTubeが登場して、1年半くらいずっとかぶりついて観(み)ていたら、退屈で身体が動かなくなったことがあります。留年もしましたし。でも、退屈だなぁ、というよりも、焦りや後悔があった気がします。
伊藤:ぼくは退屈の極みまで行ったせいか、「退屈するのって、大事だな」と当時思いましたよ。
よく覚えていますけれど、夏休みに、父親に電話をしました。もちろん、退屈だとは言えないんだけれど(笑)、「そろそろ、お手伝いしましょうか」って。父はまあまあな商売をやっていたので。
そしたら父がさ、「おまえのためにもならんし、俺のためにもならないから、自分で就職しなさいよ」って言って。
──偉いですね、お父さん。
伊藤:へぇ〜と思って。「いいの? 跡継ぎいなくなっちゃうよ?」って食い下がったんだけれど、「いいの」と言われて。その場でぼくは、就職活動を始めました。もちろん、学校の推薦なんかとても受けられないし、単身、「ぼくのことを雇ったらどうですか?」って言って回った。
──これまでのお話を伺っていると、ずいぶんと、軟派の感じがありますね。よく遊んでいる、というか。
伊藤:そうですよ、毎晩、六本木に行っていましたし。当時の六本木は、文化的に、とても良かったですね。友だちの半分以上は、ドイツ人とか、アメリカ人とか、チリ人とか、結構グローバルでしたね。大使館で働いているやつとか、いろいろいました。ビールを飲んで、遊んでいただけですけれど。やっぱり、良かったですよね。

モヤモヤとの付き合い
──就職したのち、あまり時がたたないうちに、自分の会社を創りますよね。
伊藤:小さな商事会社に入って、たぶん、2年半くらい働いたんじゃないかな。海外へよく通って、いろんな買い付けをしていました。「なんだ、仕事って簡単だなぁ」なんて思って。でも、自分で何かをやろう、とは思ってもみなかったです。
会社の社長とミャンマーへ行ったときに、とあることで大喧嘩(おおげんか)になっちゃって。日本に帰ってきたら、ぼくが尊敬している先輩の女性スタッフから「あんた、もう辞めて、自分でやんなさいよ」と言われた。ぼくは「あぁ、そうなんだ」と思って、「じゃあ」と自分でやることにした。
よく「どういうビジョンで始めたんですか?」って聞かれるんですけれど、ぼくはだいたい誰かに背中を押されているだけです。何をやる、というのが特にあったわけじゃないんです。「まぁ、自分で何かやるか」って感じ。そして、仲間と会社を創ったんじゃなくて、ぼくが創って、誘った。そしたら、3人くらい来ちゃったんだよね。
──お話を伺っていると、その頃の伊藤さんが社長だと……ビビりますね。未来を描いていない感じが。
伊藤:そりゃあ、そうだよね。金なし、信用なし、仕事なし、車なし。電話ぐらいはあったかな。
いろんな人に紹介されて会うたびに、なんでも仕事にしていった、という感じです。何屋さんになろう、という気がそもそもないですからね。何をやりたいか、よく分かっていないですから。だから、「当時はどういうビジョンを?」って聞かれると、本当に困っちゃう。
渋谷に事務所を初めて借りて、そこがビルの9階でさ。やることなくて、3人くらいで紙ヒコーキを飛ばしていた時代ってありましたよ。紙ヒコーキを飛ばして、「誰が一番長く飛んでたか?」って、100円を賭けていた時代がありました。
──「現在の伊藤守」に、つながっているようで、まだつながっていないようにも思えます。
伊藤:ぼくの言い方が軽いけれども、もちろん、それなりに考えていたんだろう、とは思うんですよ。
ただ、コンシャスネス(consciousness)というか、意識というのが、そうくっきり、ハッキリとしていないんですね。「自分」というものも、よく分かっていないし。他の人と自分との差、というのも分かっていなくて。モヤモヤしている状態だったんだな、と思うんですよ。
今、振り返ると、そういうモヤモヤしている状態が、非常に良かったですね。
──ぼくは、くっきり、ハッキリとすることを人から求められてきましたし、自分もそうなりたいと思いますが。就職活動や転職活動って、その連続です。
伊藤:学生のときからそうなんですが、「私はこうして、こうして、こうなります」って奇麗に整理されている人たちの話を聞いていると、「立派だなぁ」と思ったけれど、「そうなりたい」と思ったことは、ぼくは一回もないんですよね。
──先ほど、大学5年生の退屈の極みの話がありました。伊藤さんのモヤモヤのスタートっていつ頃なんですかね?
伊藤:むしろ、高校の頃のほうが、少し、ハッキリしていたかもしれないです。山形にいて、外の世界が狭かったし。音楽と本と友だちと、やっていることも単純で、比較的ハッキリしています。
──大学生になって、さまざまなことを吸収していくわけですが、モヤモヤはあるんですか?
伊藤:モヤモヤしているんですよ。クリアな時代もあるんですけれど、全体としてモヤモヤしている。自分が主体化していませんからね。主体化するためには、自分自身をエンゲージする(従事させる)パーパスが必要なので。
何に主体化したらいいか分からないので、モヤモヤしているわけなんですよ。でもぼくは、マルクスやエンゲルスに主体化したわけでもないし、毛沢東に主体化したわけでもないし、ケインズに主体化したわけでもないんですよ。
──就職しても続きますか。
伊藤:サラリーマンになって、「会社で仕事をするのは、結構面白いな」と思って、その頃は、少しハッキリしてくるんですけれど。いつしか、「この会社の社会的存在意義って何なんだろう?」みたいなことを考え始める。当時はそんな言葉ではなかったけれども、そういうことが分からないと、ぼくはまたモヤモヤする。そんな感じです。だから、何も、くっきり、ハッキリしていないよね。

特別なきっかけで、動いたことがない。
──『こころの対話』の中のエピソードで、すごく印象に残っているものがあって。伊藤さんが27、8歳の頃、コミュニケーションのトレーニングに参加したときもので。
伊藤:アメリカ人の友だちに誘われて、その頃、流行(はや)っていたセミナーやトレーニングへ、いくつか行ったんですよね。
──そこで、20歳くらいの女性とペアを組んで、お互いに自分のことを交互に話すゲームがあった、と。
なにしろ、当時のわたしは、27、8の生意気盛りで、20歳そこそこの女の子とは、デートをするのはいいけれど、自分のことを真面目に話すなんて、とんでもない、話したってむだだと決めつけていたんです。
最初は、彼女の番で、彼女は自分のこれからの人生について、いまかかえている問題について、一生懸命話してくれました。わたしは、「うん、うん」とうなずきながら、聞いていました。次に、わたしの番が回ってきたとき、もちろん、真面目に話す気なんてありませんでしたから、確か、油揚げの話かなんかしました。油揚げは、そのまま焼いて、醤油をじゅっとかけて食べるのがいちばんおいしいとかなんとか。
で、そのゲームを終えて、休憩時間になって、わたしが別の人としゃべっていると、だれかが、とんとんとわたしの肩を叩くのです。振り返ると、その女の子がたっていました。目に涙をいっぱいためて。
「どうしたのー?」と、年上らしい余裕で、尋ねると、彼女が言いました。
「伊藤さん、あなたって、人の話を聞かない人ですね」
「えっ、そんなことないよ。きみの話はちゃんと聞いてたよ」
わたしはそう言って、彼女の話をほぼ正確に、復唱してみせました。
「ねっ、聞いてただろ?」
すると、彼女は、ますます涙の粒をふくらませて、言いました。
「ほら、いまだって」
※引用:伊藤守『こころの対話』より(講談社、1995年)
伊藤:そして、ムッとしながら家に帰ったんですよね。内心、穏やかではなかった。
当時は、9つ下の妹と同居していて、その日起こったことを妹にしゃべったんです。「ぼくは人の話をちゃんと聞くほうだろう?」と妹に聞いたら、「うん、聞く、聞く」って。繰り返すのがどうも嘘(うそ)くさいですよね。
「なんか正直に言ってみろよ」と言ったら、「やだ」って妹は言うんです。「なんでだ」と聞いたら、「本当のことを言うと、お兄ちゃんは怒るから」って。ますます、ぼくは動揺しました。
「怒らないから言ってみろ!」と言ったら、「そうやって怒るから嫌なのよ」って言われてね。何か腹に一物があるんだな、と思って、どうにか、妹から聞いた言葉が、「お兄ちゃんって、いっしょにいても、いない人」という言葉でした。
その夜は、眠れませんでした。それから3日間、自分がどのように過ごしていたのかわかりません。ただ、自分の中で、何かが大きく崩れ、自分でもどうしていいのかわからない状態が続きました。
それでいて、不思議なのですが、自分がとても安心していることにも気がつきました。動揺はあるのですが、もうこれ以上妹に、優秀な兄、ものわかりのいい兄、妹思いの兄、それらの演技をする必要がなくなったこと、そして、自分がいま、どの位置にいるのかが自分の中ではっきりしたことに、ほんとうに安心していたのでした。まわりの人にほめられたり、頼りにされることでは手に入らなかった安心感が、そこにはありました。わたしは、安心感について誤解していたようです。
※引用:伊藤守『こころの対話』より(講談社、1995年)
──この出来事があったことで、伊藤さんにとって「コミュニケーション」が決定的なテーマになったのかな、と思いました。
伊藤:あのね、そういう特別なきっかけで、ぼくは動いたことがないんですよ。
当時は「ダイアローグ」という言葉で出始めている頃で。心理学の世界も、エリック・バーンの交流分析や、アルバート・エリスのイラショナル・ビリーフ(不合理な信念)とか、フレデリック・パールズとか、その当時、どんどん出てきていたんですよね。60年代終わりから、70年代って。
そういう本を読んでいる中で、「とどのつまり、めんどくさいのは、人との関わりか」という感覚を持っていました。そして、「コミュニケーションというのは、フィーリングの問題ではなくて、ケイパビリティ(Capability)なんだ」と。
ぼくは、コミュニケーションのうまい人になろう、というつもりはなかったんですが、「これは、たぶん、追いかけて行ったほうが良さそうだぞ」となんとなく思っていたんです。貿易の仕事をしていても、結局、最後の最後はコミュニケーションになるんですから。
モヤモヤ感がなくなるっていうのは、人との関係において、自分の位置がハッキリしてきたり、どうも、なんか、もうちょっとあるらしいぞ、と思い始めたりするんですよね。

「奇麗に整理されている人たちの話を聞いていると、『立派だなぁ』と思ったけれど、『そうなりたい』と思ったことは一回もない」
「特別なきっかけで、ぼくは動いたことがない」
伊藤さんのお返事を聞きながら、私はとても単純化した仮説をもとに、伊藤さんへ質問を投げかけていたことを思い知り、恥ずかしくなる。そうした相手へ不遜な態度を取る自分が嫌で、コミュニケーションについて考え始め、いつしか、伊藤守さんの本にたどり着いたにもかかわらず。まるで成長していない。
今回の前編では、伊藤さんの10代〜20代のお話を伺った。次回の後編は、伊藤さんの30代〜40代前半の話を伺い、伊藤さんが大切にしてきたことを考える。用意していた仮説がたちまちに消えたことで、どんどんと自然な会話が増えていく。
(後編へ続く)
・「死んじゃった人を信じるのは、簡単。生きている人を信じるのが、難しい」──伊藤守さん(後編)
【撮影:保田敬介】
【特集:あなたのキャリアに一目惚れしました。】
・「生きもの」感覚を大事に、「いい大人」とめぐり会い、「一生考えましょうよ」──中村桂子さん(前編)
・一生懸命に生きている「いい大人」と出会う。そして、一生考えることが、好きになる。──中村桂子さん(後編)
・結婚・出産で就活断念。「予期せぬ出来事」は、キャリアを強くするきっかけになる──太田彩子さん
・「役に立たない」は未来へのバトン。だから私はキリンの解剖が続けられている──郡司芽久さん
・「あのね、ぼくは、そういう特別なきっかけで、動いたことがないんですよ」──伊藤守さん(前編)
・「死んじゃった人を信じるのは、簡単。生きている人を信じるのが、難しい」──伊藤守さん(後編)
・湯上がりの幸せを、ずっとこの先も。僕らの未来を広告でなく銭湯で守りたかった【小杉湯・ガースーさん】
・「留年して、建設省への就職がおじゃんに。それで大学院のあと、野村総研へ入るんです」 山形浩生さん(前編)
・「誰も何も言わない世界と、読まれなくても誰かが何か言う世界は、多分違う」──山形浩生さん(後編)
・「なんで急に落ちこぼれになったんだろう?」苦しかった就職活動と可能性が広がった20代──今井麻希子さん(前編) ・「見つかっちゃった!出会っちゃった!」やりたいこととの衝撃的な出会い──今井麻希子さん(後編)