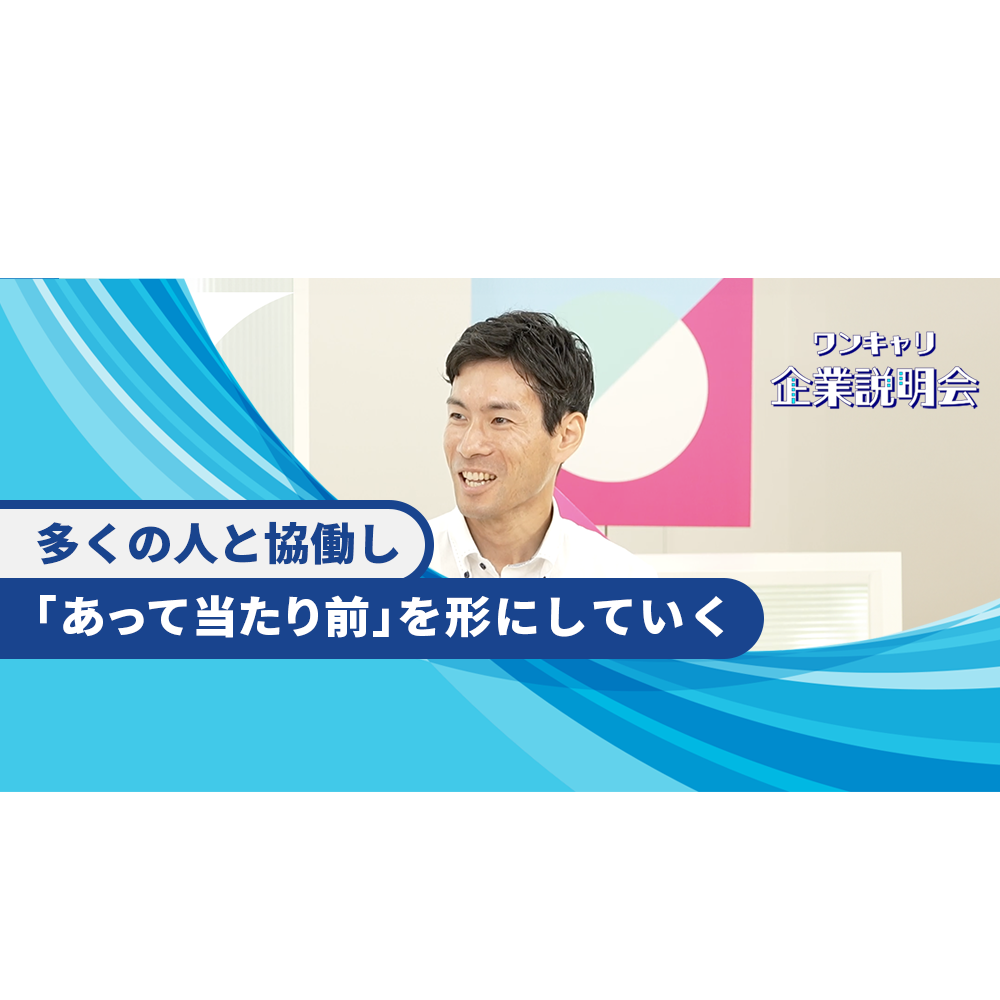新型コロナウイルスの感染拡大によって、さまざまな企業が苦境に立たされる中で、景気の減退も心配されています。
「アフターコロナの業界研究」として、今回ワンキャリア編集部が着目したのはスタートアップです。
景気が悪くなれば、投資は鈍りやすくなるはず。苦境に立たされている企業は多いのではないか──そう考え、資金面や知識面でスタートアップを支援するベンチャーキャピタル(VC)に聞いてみたところ、意外な答えが返ってきました。
「いえいえ、変化を追い風に業績を伸ばした企業も多いですよ」
取材に応じてくれたのは、アーリーステージのスタートアップ投資をしている「Coral Capital」でタレントマネージャーとして投資先の採用支援などをしている津田遼さん。
新型コロナで世界が大きく変わる今、VCが注目しているスタートアップはどこなのか。新卒での就活先としてスタートアップを選ぶ際に、何を軸に考えれば良いのか。ベンチャーキャピタルの視点から迫ります。
連載:「アフターコロナ」の業界研究
新型コロナウイルスの感染拡大により、打撃を受け、変化を余儀なくされる業界は少なくありません。この連載では、各業界の企業を取材し、ビジネスへの影響と復活へのシナリオ、そして各業界の「ニューノーマル」の姿を浮き彫りにしていきます。
新型コロナは、多くのレガシー産業の変革に挑むスタートアップの追い風に
──本日はよろしくお願いします。最初から直球の質問になってしまうのですが、新型コロナウイルスの影響で、苦しんでいるスタートアップは多いのでしょうか?
津田:もちろんケースバイケースですが、逆に追い風になっているところも多いです。観光関連など、新型コロナの負の影響を受けやすい事業を展開している企業は厳しい一方で、事業によってはコロナ禍を機に業績を伸ばしているところもあります。
 津田 遼(つだ りょう)
津田 遼(つだ りょう)
株式会社Coral Capital タレントマネージャー。早稲田大学法学部卒業。日本GE株式会社のファイナンス部門でFP&Aアナリストとして経験を積んだ後、グリー株式会社に人事として入社。グリーでは、中途採用、組織人事(HRBP)、米国子会社人事などに従事した後、500 Startups Japanに参画。Coral Capitalでは500に引き続き、投資先スタートアップの採用支援とコミュニティ構築・運営を行っている。サーフィンと温泉をこよなく愛する。
──そうなんですか? 事業基盤が未熟なスタートアップは、影響を受けやすいものだとばかり思っていました。
津田:例えばCoralの投資先には人事・労務手続きを効率化させるSmartHRのように、レガシー産業をITの力でより良い方向に導くDX(デジタルトランスフォーメーション)に挑戦しているスタートアップもあり、そういった多くのスタートアップはコロナ禍でも順調に事業を伸ばしています。
最近はいわゆる「脱はんこ」の動きが加速しているように、新型コロナをきっかけに非効率的だった業務を見直す動きが出てきています。「大企業が解決できないような業界課題に素早く切り込める」というスタートアップの強みが生かされた形ですね。
他にも、例えばこのタイミングでさらに成長を加速したスタートアップには、行政サービスのデジタル化(GovTech)を進める「Graffer(グラファー)」や、10代〜20代前半の女性に利用者が多い化粧品ECの「NOIN(ノイン)」などがあります。
彼らの事業に共通するのは、「対面」が慣習だった業界の変革を進めている点です。コロナ禍において、会わなくても済む手段が求められていることから、サービス利用者がグッと伸びています。
──とはいえ、VCは大変ですよね。新型コロナによる影響も追い風にして伸びているスタートアップが多いとはいえ、この先3〜5年については、どこも成長予想を立てにくいのではないでしょうか。
津田:確かにアフターコロナの世界は予測がしにくい面はあります。ただ、私たちの感覚としては、これで未来の方向性がガラリと変わるものでもないと思っています。
例えば、ビデオコミュニケーションプラットフォーム「Zoom」の急成長などはそうですよね。驚いた人は多かったと思いますが、コロナ禍がなくとも、ゆくゆくはそうなるだろうと皆思っていたでしょう。単にそのタイミングが早まっただけに過ぎません。
それにこの状況がずっと続くわけでもないはずです。対面型のサービスも含め、新型コロナの影響で今波が引いている産業もアフターコロナで勢いは戻ると予想しています。
成長領域で働きたいなら、まず将来の「市場規模」を把握しよう
──なるほど。では、そうした可能性も踏まえ、津田さんが今注目している領域はありますか?
津田:Coralとしては「良い起業家や事業があれば投資する」というスタンスで、さまざまな業界や領域のスタートアップに成長のチャンスがあると考えています。
実際、投資先にはリーガルテックやHRテック、ガブテックなどさまざまな企業がおり、レガシー産業のDXを目指す企業以外にも多く投資をしています。例えば最近は、ウォルト・ディズニー・ジャパンとの連携が決まったバーチャルヒューマン事業を展開する「Aww」というスタートアップにも投資しています。

※出典:Coral Capital「Portfolio」
──確かに、さまざまな領域がテクノロジーによって大きく変わる可能性がありますよね。興味がある領域を見つけた後は、どんなことをすれば良いでしょうか?
津田:スタートアップで働く以上、成長産業の成長企業で働くことで常に新しい挑戦が発生し、自らの成長にもつながってくるので、そういった点でまずはその業界の「市場規模」が大きく、将来もさらに大きくなっていくかを予想することが重要になると思います。
──確かにこれはスタートアップ志望ではなくても、企業を選ぶ際に就活生に考えてほしいことですね。
津田:私たちの中でも「この業界ではDXが進みそう」という予測はあります。例えばアメリカで同じようなサービスを扱うスタートアップが伸びている、とか、似たような構造の産業でDXが進んでいるとか。各社との情報交換で見えてくる部分はあります。
全ての業界を高い精度で予想することは、私たちでも難しいですが、少なくとも「これからの業界がどうなりそうか」という予測をいろいろな公開情報を元に立てるのは大切です。もし迷ったときは、Coral Capitalがやっている「Coral Insights」というブログをはじめ、各VCの情報発信やキャピタリストが個人で書いているnoteなどを読んでみるのも参考になると思います。
VCの投資検討でも使う視点──伸びるスタートアップを見極める「3つのポイント」
──「伸びる業界」の予想することが大事なのはわかりました。では、その伸びる業界にいる「伸びるスタートアップ」を予想するにはどうすれば良いのでしょうか?
津田:結論から言うと、それを100%の精度で見極めるのはわれわれでも無理です(笑)。ただ、私たちが投資検討をする際に用いる3つの判断軸は、学生の皆さんが伸びるスタートアップの予想を立てるのに役立つと思います。

──面白いですね。簡単で良いので教えてください!
津田:それは「マーケット予測」「ファウンダーマーケットフィット」「代表が人を巻き込む力」の3つです。1つ目の「マーケット予測」は先ほどお話しした市場規模と成長の予測と同じです。
2つ目の「ファウンダーマーケットフィット」というのは、ファウンダー(起業家)がそのマーケットにフィットしているか、つまり、そのファウンダーだからこそ、そのマーケット、その事業で勝つことができる必然性はあるのかということです。
──どういうことでしょう?
津田:例えば、頭がキレキレで聡(そう)明で、コミュ力も高く、人格者でもある戦略コンサル出身者の方が食糧業界のスタートアップを立ち上げるとしましょう。スペックは非常に高い方ですが、その方が必ずしも事業を成功させられるかと言うと、そうではありません。事業を成功させるには、その業界の課題を深く知っている、業界の力学に精通していて、その界隈(かいわい)の人たちに対し営業や説得が行える、などといった力も求められます。
起業をする以上、事業のアイデアが他社と被ってしまうこともあるかもしれません。そんな場合でも「この人なら勝てる」というポイントがあるかが大事です。
──3つ目の「代表が人を巻き込む力」についてはどうでしょうか。
スタートアップを創業メンバーだけで成功に導くのは不可能であるため、優秀な人を集め、チームを作ることが求められます。
漫画の『ONE PIECE』みたいに、適材適所に強力なメンバーを巻き込めるかが試されるわけです。リーダーシップと一口にいってもいろんな魅力の出し方があるため、この形は起業家によって十人十色ですが、そういうものを代表から感じられるかどうかが重要です。
──これら3つの要素の中で、一番判断が難しいのはどれだと思いますか。
津田:3つ目の人を巻き込む力でしょうね。残り2つはマーケットサイズや、経歴、業界への知見の深さなどといったファクトから一定の予想を立てていくことができますが、3つ目については実際に会って、言語化できないものを感じ取って自分の経験則から判断しなければいけません。
新卒ならば「活躍できるか」「自己成長できるか」も企業選びの柱になる
津田:ここまで「伸びる可能性が高い市場」「伸びる可能性が高いスタートアップ」を見極める方法について話をしてみましたが、新卒での就活という文脈においては、それと同等かそれ以上に「自分がそこにマッチするか? そこで成長できるか?」ということを見極めることがとても重要だと思っています。
──「自己成長できる企業かどうか」が新卒には重要だと。
津田:確かに、運良くこれから伸びるスタートアップに入って社内の信頼を勝ち取ることができれば、そうでない企業に入るよりも多くの挑戦の機会に恵まれ、大きく成長できると思います。
ですが、最初に話したように、次のユニコーンを見極めるのはそれを商売にしているベンチャーキャピタルですら難しいです。そして、そういったスタートアップに運よく入社できたとしても、そこで活躍して社内の信頼を得ることができなければ、そういったチャンスも回ってきません。だから「どんな環境に自分はマッチしているのか? どんな環境だと最も成長できるのか?」ということをしっかり考え、見極めることが大事です。

──その環境に自身がマッチするかを知るには、どうしたら良いでしょう。
津田:自分の学生時代の活動を振り返り、「自分がどんなときにワクワクしたか(興味)? 人よりも努力せず高いパフォーマンスを自然と出せたのは何か(強み)? それはどんな時に一番発揮されやすかったか(強みを引き出す環境)?」を知ることが大事だと思います。
やり方はいろいろあるので、自分に合うやり方を見つけてもらえれば良いと思いますが、僕の場合は、今話した3つの条件について思い当たるものをノートにバーッと書き出していき、そこから導き出せそうな仮説を立て、それを基にさまざまな企業の人に会ったり、自分のことを深く知っている人にぶつけてみたりして検証するというスタイルで、仮説の精度を上げていきました。
ただ、かく言う僕は、就活のときはそれが全然できておらず、転職をする時にようやくできました。「言うは易く、行うは難し」だと思います(笑)。
キャリアを切り開く覚悟と行動力に自信があるなら、新卒スタートアップも見えてくる
──学生の中には、メガベンチャーをファーストキャリアの候補に入れるケースも少なくありません。スタートアップを選ぶこととの違いを教えてください。
津田:良いメガベンチャーは一言でいうなら「人の層が厚い」です。プレイヤーやマネージャーを含めて優秀な人が多く、入社後もOJTなどでしっかり教育してもらえる環境にあります。
一方、スタートアップは教育環境が整っていないケースが多いです。そういった中で成長するには、自分から主体的に先輩や上司を巻き込んで積極的にフィードバックをもらうようにしたり、自分の強みや弱みを自覚した上で、時間をかけて磨いていく分野を自分の意思で決めて行動したりする必要があります。
そのため、自分の力でキャリアを切り開いていきたい人、そしてそれができる人には向きますが、逆にその気概と行動力がなければ、スタートアップはやめた方が良いと思います。
──この記事を読んでスタートアップに興味を持った学生がいたら、まずはどうしたら良いでしょう。
津田:Coral Capitalの投資先もそうですが、特にアーリーステージのスタートアップだと即戦力を求めているので、新卒採用をしていない企業が多いです。そのため、まずはインターンとして応募するのが良いと思います。企業を知るのはもちろん、1社目にスタートアップを考えていない人でもノーリスクで経験を積むことができます。Coral Capitalのインターン生の中にも、就職先は大企業ですが、経験を積むために参加しているという学生もいます。
──今の津田さんなら、どのような基準でインターン先を選びますか?
津田:前提として、私自身、インターンは必ずやるべきだとは思っていません。旅をしたり遊んだりするのも良いことですから。あえて、それでもインターンをするなら、起業した直後、アーリーステージの企業に入りたいです。起業家の近くで「世の中を変えようとする人がどんな人生観を持っているのか」などを知りたいですね。
そうした経験から「こうなりたい」「ここは自分の方が良い」という軸が持てるようになると思います。転職を検討するときの判断材料になるため、大手を志向している人にとっても有益なはずです。
──ありがとうございました。最後にこの記事を読む学生に対し、メッセージをお願いします。
津田:私は日々、スタートアップへの転職希望者とお会いしますが、新卒からスタートアップに入社して活躍をする人は極めてマイノリティです。情報感度の高い、一部の学生の皆さんの中には「スタートアップに行く人はイケてる、大手に行く人はイケてない」みたいな空気があるかもしれません。
その風潮に対して私が言いたいのは、「新卒就活の時点でスタートアップに向いている人はスタートアップで働けば良いし、向いていない人は無理に行くべきではない」ということです。
Coral Capitalの投資先のアーリーステージのスタートアップで活躍している多くの方が、新卒では大企業やメガベンチャーなどに入り、そこで経験を積んで武器を磨いた上で、スタートアップに興味を持って転職をしてきている方です。
さらには、新卒で商社に入り、そこからスタートアップを起業した方もいます。変な見えやはやりに流されるのではなく、自身の軸をしっかり見つめて、自分が本当にマッチする環境を愚直に考えて行動して探すことが一番大事だと思っています。
【アフターコロナの業界研究】
・【新連載スタート】新型コロナで一変した業界地図、識者たちが各業界の「ニューノーマル」を読み解く
・ぶっちゃけ、コロナ後もオフィスビルの需要ありますか? 三菱地所とアフターコロナの街づくりを考える
・コロナ禍で旅行が封じられたJTB、過去最大のピンチをどう乗り越えるのか?
・定期券を新時代のサブスクに──新型コロナに苦しむ「私鉄の勝ち組」東急、逆転のシナリオ
・コロナ禍の今、イケてるスタートアップはどこ? ベンチャーキャピタルに聞いてみた
・デジタル人材は救世主となるか。新型コロナで経営窮地のマスコミが狙う起死回生の新ビジネス
・本当の危機はコロナ禍の「先」にある──星野リゾートは世界と戦えるホテル運営会社になれるのか?
・時短要請や接触回避も「制約」の一つに過ぎない──外食の雄、サイゼリヤに学ぶコロナ禍との付き合い方
・家だけじゃない、どこでも荷物を受け取れる時代へ──コロナ禍で変わる業界の常識、ヤマト運輸に宅配の未来を聞く
・休業2カ月で40億円の損失? 外出自粛で苦境の書店業界、「有隣堂」が生き残る道を聞く
・コロナ禍で激減した飲み会、酒類業界復活のカギは?キリンビールが見出した「2つの突破口」
・「コロナ休校」の裏で進んだベネッセの変革。少子化の先にあるビジネスチャンスとは?
・コロナ禍で「ラジオ人気」に火がついた 「オールナイトニッポン」プロデューサーが考える、音声コンテンツの未来




















.png)