※こちらは2019年2月に公開された記事の再掲です。
こんにちは、ワンキャリ編集部です。
世界屈指の広告企業である電通と、米国発のイノベーションをリードするGeneral Electric Company.(GE)のDNAをあわせ持つIT専門家集団を知っていますか?
ワンキャリアは電通国際情報サービス(Information Services International-Dentsu, Ltd.以下、ISID)を総力特集。全3回にわたり、同社の魅力に迫ります。
第3回となる今日は、同社技術本部において技術開発・事業支援を担う技術者として働く、中川洸佑さん(写真右)と荻原直祐さん(写真左)にお話を伺いました。中川さんはXR領域の研究開発グループのリーダーを務め、荻原さんはUXデザインのエキスパートとして活躍しています。
<用語解説>
・XR: AR(拡張現実)、MR(複合現実)、VR(仮想現実)などの技術の総称
・UX:ユーザーエクスペリエンス。個人が製品やサービスを通じて得る全ての体験。UIの操作といった利用体験そのものだけでなく、利用前の期待感や利用後の満足感などもUXに含まれる
・UI:ユーザーインターフェイス。製品の操作部や画面、操作に応じたフィードバックなど、ユーザーと製品のコミュニケーションを媒介する接点のこと
最先端の技術を駆使したプロジェクトの内容から、「請負仕事はクリエイティビティを発揮しにくい」という先入観を打ち破るリアルな業務の実態まで、テクノロジーとビジネスの融合に興味を持つ方は必見の対談です。
「XR領域」×「UXデザイン」エキスパートたちが語る、開発現場のリアル
──今日はよろしくお願いします。まず、お二人がISIDの技術者として、普段どういったお仕事をしているのか教えていただけますか?
中川:新卒でISIDに入社し、現在4年目です。私たちの所属する技術本部 開発技術部は、技術調査・研究を幅広いテーマで行っている部門です。
私はそこでVR(仮想現実)/AR(拡張現実)に関する研究開発グループのリーダーを務めています。同時に、弊社製造ソリューション事業部での職務も兼務していて、主に自動車メーカー向けにVR/ARの活用支援を行うプロジェクトにも参画しています。
両方とも5人ほどのチームで、いわゆる上流工程にあたるシステムの企画・設計をメインに担当しています。プロジェクトによっては、実装から展示会でのプロモーションの支援まで幅広く担当していますね。XR技術をより広めていくために、外部の勉強会やイベントに登壇することもあります。
中川 洸佑(なかがわ こうすけ):2015年入社。技術本部 開発技術部にて、XR技術の調査・研究開発を担うグループのリーダーを務める。兼務する製造ソリューション事業部では、自動車業界における技術活用を推進するプロジェクトにエンジニアとしても参画。ISIDにおけるXR技術の第一人者として、社内外のイベントでトレーナーやプレゼンターも務める。(所属部署はインタビュー当時のものです)
荻原:UXデザインのエキスパートとして、製品やサービスのコンセプトを決めるためのユーザー調査・分析から、コンセプトにもとづくUIデザイン、UIとしての使いやすさ(ユーザビリティー)の評価などを、部署を横断して担当しています。
関わる対象はお客様のプロダクトやWebサイトから、中川が取り組んでいるような自社の研究開発まで幅広いです。現在は4人のチームで、ユーザーインタビューやUIデザインを分業しつつ、柔軟にプロジェクトに携わっています。
荻原 直祐(おぎわら なおすけ):UXデザインコンサルティングファームを経て、2008年入社。UXデザインを軸に事業支援を行うグループのリーダーを務める。ISIDの製品・サービスのUI設計に広く関わり、社員のデザイン思考トレーニングや研修の企画も担当している。(所属部署はインタビュー当時のものです)
XRが「働き方」と「モノづくり」をアップデートする
──お二人の業務内容について、もう少し詳しく教えてください。
まず中川さんからお聞きします。VR/ARというと、ゲームや映像コンテンツなど、エンターテイメントの分野で使われている印象が強いです。ビジネスの現場では、どのような活用が見込めるのでしょうか?
中川:実用化に向けて実験を進めている試みの一つに、VR/ARとロボットを組み合わせた、ハードウェアのパフォーマンスの拡張があります。
清掃ロボットを例に説明しますね。一般に普及している製品はハードウェアに組み込まれているセンサーが障害物やゴミを認識しています。しかし、人の目に比べてロボット(ハードウェア)のセンサーの精度はまだまだです。全て人力で清掃するのは面倒だけれど、ロボットでは行き届かない部分までうまく清掃したい……。そんな時にARの技術が役立ちます。
中川:例えばオフィスの清掃ロボットを管理する人が、ヘッドマウントディスプレイ(写真上)を装着します。複数台のロボットに清掃を任せながら、「ここにある汚れを取ってほしい」と思う場所を視線やジェスチャーで指定すると、ロボットがその場所に向かい、掃除をしてくれます。視線や動きを使って、直感的にロボットへ指示することができるのです。ARがいわば「人とロボットの橋渡し」的な役割を果たすということです。現状の製品でも現実空間とARを組み合わせることで、できることを増やせるんです。
──それは面白いですね! 他に、VR/ARで将来的にどんなことができるようになりますか?
中川:さまざまな可能性がありますが、私はその中でも二つに注目しています。
一つは、働く上での時間的・空間的な制約を減らせることです。VR/ARで会議を行えるようになれば、離れた場所でも参加者同士が細かな身ぶりや表情の変化を捉えたコミュニケーションを取れるようになります。
また、VR空間での動きを記録して他の人に共有できるようになれば、時を同じくせずとも、鮮明に体験をシェアできます。ビデオ会議やチャットツールを駆使してリモートワークをする人は現在も少なくありませんが、VR/ARを使えば、より多くの情報を共有し、空間的に離れていてもリアルタイムでなくても、現実に近いコミュニケーションが実現できるかもしれません。
──もう一つについても教えてください。
中川:二つ目として、モノづくりのスピードが加速すると思います。具体的には、VR/ARによって、従来よりさらにプロトタイプが作りやすくなります。現在は自動車を設計するにも、3Dソフトで作った設計を紙やモニターを通して、一度2Dでチェックしながら進めなければなりません。加えて、それを3D(立体)で確認するために実機を作ろうとすれば、多大な時間とコストがかかってしまいます。
もしVR/AR空間上でこの設計を確認できるようになれば、実寸大の3Dプロトタイプを一瞬で目の前に投影できます。VR/ARでリアルタイムに車体のカラーや内装・外装に変更を加えていくこともできるので、より柔軟で素早い製品開発が実現できます。
幅広いプロジェクトに関わるからこそ、UXデザインの本質に向き合える
──荻原さんにもお聞きします。UXデザインのエキスパートは、ISIDでどのように活躍しているのでしょうか。印象に残ったプロジェクトを教えてください。
荻原:5年ほど前に、大手銀行のインターネットバンキングのシステムを改修したことです。当時のインターネットバンキングは、ATMの操作画面をそのままアプリに移行したようなデザインで、とにかく使いにくかった。スマートフォンやアプリの操作に慣れ親しんだ人にとっては、特に「イケてない」使用感だったはずです。それを1年ほどかけて、ユーザビリティーの観点から使いやすく変えていったんです。
週に一回はお客様と直接話す場を持ち、手書きのラフ案の段階から丁寧にすり合わせて改修していきました。日本中で多くの人に使われるシステムをよりよいものに改善できるプロジェクトは、社会的なインパクトが大きいこともあって、非常にやりがいがありましたね。
──「UXデザイン」と聞くと、スマートフォンアプリのようなBtoCサービスが例に挙がることがほとんどです。BtoBサービスの場合は、どんな違いがあるのでしょうか。
荻原:BtoCでもBtoBでも「ユーザーが使いやすいサービスを作る」という原則は変わりませんし、UXデザインの方法論も、基本的には同じです。
違いがあるとすれば、BtoBの場合は、お客様の業界や業務にまつわる専門知識を理解する必要があります。例えば金融系の業務システムのUIデザインを行うのであれば、金融用語だけでなく、社内で使われる専門用語や業務慣習まで知っておく必要があります。日常的に使うツールの使いやすさを追求する立場だからこそ、前提知識のインプットが求められます。
──身につくスキルの面ではいかがでしょうか。クライアントを相手にする案件は、レベル感もさまざまな要望に応えなければならず、自社製品の開発案件と比べて自由度が低い印象があります。UXデザインのエキスパートとして成長しにくいのではありませんか?
荻原:むしろクライアントワークを通じて幅広いサービスに関わった方が、UXデザインの本質に向き合う経験を多く積めると思います。
事業会社で一つのサービスのUXを担当していると、ローンチ後はKPIを達成するための細かい改修が中心になりがちです。それに対してクライアントワークでは、上流の提案段階からさまざまなサービスのコンセプトメイキングに繰り返し関われます。お客様の課題を起点にUXデザインを行う「おいしい経験」を積むことで、デザイナーとしての幅を広げられるのが魅力だと思います。
ISIDは電通グループということもあってか、面白い案件に次々と出会えます。XRデバイスからマグロの養殖場まで、ここまで多彩なプロジェクトを担当できる会社は、他にないと思います(笑)。
プロフェッショナルとして尊重されるので、「ブラック」になりえない
──関連して、突っ込んだ質問もさせてください。トップ就活生へのヒアリングによると、IT技術職(SE、ITコンサルタント)は一括りに「下請けゆえに、裁量や独自性を発揮する場がない」「低い生産性で、精神的プレッシャーも大きいブラックな職場」という先入観を持たれています。その点についてはどうお考えですか?
中川:下請け的な不自由さは、一切感じたことがありませんね。そもそも私たちが声を掛けていただく時は、専門家としてアドバイスが求められるタイミングです。お客様の知識だけでは分からない点があるからこそ頼っていただけているので、ポジティブに話を聞いてもらえます。プロの知見を提供する立場である以上、頭ごなしに意見がつぶされるようなことはまずありませんよ。
荻原:私も同じですね。初めはあまり関心を示してくださらないお客様であっても、ユーザビリティーの理論をお伝えしたり、ユーザーインタビューやワークショップに同席してもらうことで、私たちの取り組みをご理解いただけますし、プロフェッショナルとして尊重されているのを感じます。「見栄えのよいデザインを作る係」ではなく「どういった機能を持つシステムを作るべきか?」という大前提からお客様と議論しているからこそ、得られる関係だと思います。
中川:労働環境面の「ブラックさ」も特にありませんね。部署や時期によって多少の差はあると思いますが、私が所属している部署は、むしろ「残業することが難しい」環境です。先輩たちも含めて、勤務時間内にしっかりパフォーマンスを発揮し、きちんと評価も受けています。帰ると決めた時間には帰って自分の時間も大事にする、という働き方をよしとする人が多い気がします。大学の研究室時代の方が、よほど厳しい生活リズムだったと思います(笑)。
「絵に描いた餅」で終わらない、ISIDの実行力とネットワーク
──そもそもお二人は、なぜISIDに入社したのでしょう?
中川:「人」が魅力的だったからですね。もとからIT関係に興味があり、ITコンサルやSIerを志望していたのですが、たまたま合同説明会でお会いした社員の雰囲気がすごくよくて。私には他のIT系企業の社員さんよりも、生き生きと、やりがいを持って働いているように見えたんです。個別のセミナーに参加してみても、その印象は変わりませんでした。
荻原:「人」に惹かれたのは私も同じです。私は中途入社なのですが、前職で働いていたとき、ISIDと仕事をしたことがありました。そこで、単なる発注先ではなくパートナーとして対等に接してくれたのが気持ちよくて(笑)。ちょうど転職を検討していた時期だったこともあり、興味を持ちました。
加えて当時のISIDは、これからUXデザインに力を入れていくという時期でした。伸びしろが多く、組織の立ち上げフェーズから関われそうだと感じたのも入社の動機の一つです。
──事業面の魅力についても教えてください。志向性が似ているITコンサルやベンチャー企業と比較すると、いかがでしょうか?
荻原:前職がコンサルティング会社だった私から見ると、システムやサービスの実装まで責任を持って進められるのがSIerとしてのISIDのよさだと思います。コンサルの場合は、いかに理想的なUIを提案しても、それが最終的に実装されたか分からないまま案件が終了するケースもままあります。「絵に描いた餅」で終わらず、企画から提案、開発、リリース、運用まで、自分が担当として全てに関わることができるのは、やりがいを感じられる大きなポイントですね。
中川:ベンチャーと比べた強みは、ISIDが持っている既存のコネクションを生かせる点だと思います。自社のみで新領域に挑むベンチャーも多々ありますが、例えば他社と組んでXR開発を行うにしても、ベンチャーの場合はコネクションに限りがあります。XR技術に高い関心があり、かつその企業のことを知っている人とつながり、そこから声を掛けてもらうことができないと、連携は難しいのがビジネスの世界の実態です。一方ISIDは、幅広い業界にクライアントを抱えています。現時点でXRに関心がないお客様に対しても、既存の提案と絡めてXR技術の紹介や導入につなげていくことができます。
──ISIDのコネクションの幅広さは、第一回のインタビューでもお聞きしました。新たな領域に挑む際には、積み上げてきた関係性が強力な武器になるのですね。
やりたいことだけでなく、「一緒に働く人」も重視しよう
──ここまでのお話を踏まえて、お二人はどのような人がISIDに向いていると思いますか?
中川:難しい質問ですね。ISIDは、どんな人でも適切な役割にアサインしてもらえる懐の深さがあると思うので……(笑)。
中川:強いて言うなら、私が今いる部署のメンバーを思い浮かべてみてもそうですが、自分のやりたいことや実現したい未来を主体的に考え、周りを巻き込んでプロジェクトを進めていける人が向いていると思います。さまざまな領域のプロフェッショナルと連携しながらプロジェクトを進めていく部署なので。
ISIDは、自分がやりたいことをきちんと表明すれば、前提知識がなくてもアサインしてもらえる傾向にあると思います。私がいるXRチームも、元々は関連領域に詳しくなかった人も多いです。
荻原:自分の考えを言葉にして、積極的に伝えていける人が向いていると思います。日々、事業部のメンバーやお客様に対峙することになるので、お互いの考えをぶつけ合って化学反応を起こすことが求められると感じています。
UXデザインの観点では、さまざまな事象に問題意識を持てる人が向いていると思います。日々使っているモノやサービスにしても、漫然と利用してそれで満足しているようではダメで、自分にフィットしない部分はどこかを明らかにし、あるべき姿を自ら考えるマインドがあると、仕事にも役立つと思います。
──最後に、就職活動中の学生に向けてのメッセージを伺ってもよろしいでしょうか?
中川:やりたいことや事業だけでなく、「一緒に働く人」の観点も重視して会社を選ぶことをおすすめします。どんな職種であっても、自分一人でできることには限りがあります。だからこそ、自分が働きやすいと思えるメンバーがいるかどうかが大事になってきます。もちろん優秀な人が来てくれたらうれしいですが、それ以上に「ISIDは自分に合っている」と思ってくれた人に来てほしいと思っています。
荻原:新卒で入社した方が私のチームに入る可能性も十分にあるので、UXデザインに興味がある学生向けの話をさせてもらいますね。
いろいろなものを体験してください。体験して感じた「好き」あるいは「嫌い」な理由を言語化する習慣がついていると、UXデザイナーとして働く基礎ができると思います。
──中川さん、荻原さん、本日はありがとうございました!
【ISID:特集】
第1回:「出る杭が打たれない」会社。電通×GEが生んだイノベーションのDNA
第2回:SIerってブラックなんですか?キャリアと働き方のリアルに迫る
第3回:「最新Tech」×「UXデザイン」対談。IT専門家集団の真価がここにある
【インタビューアー:めいこ/ライター:小池真幸/カメラマン:友寄英樹】





















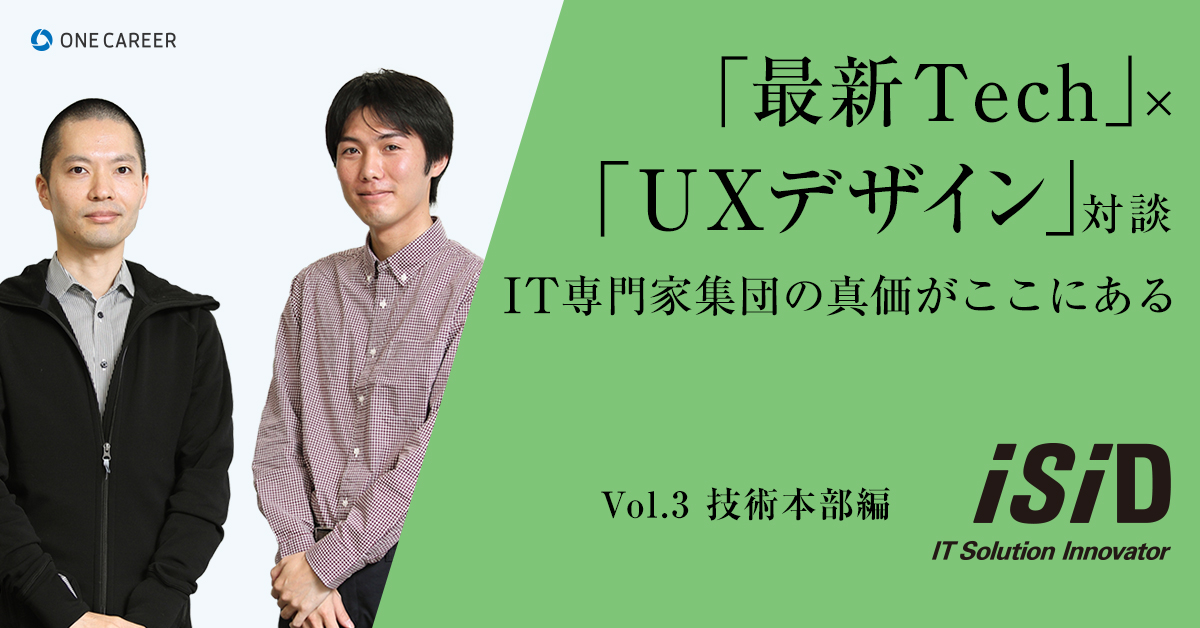





.jpg)