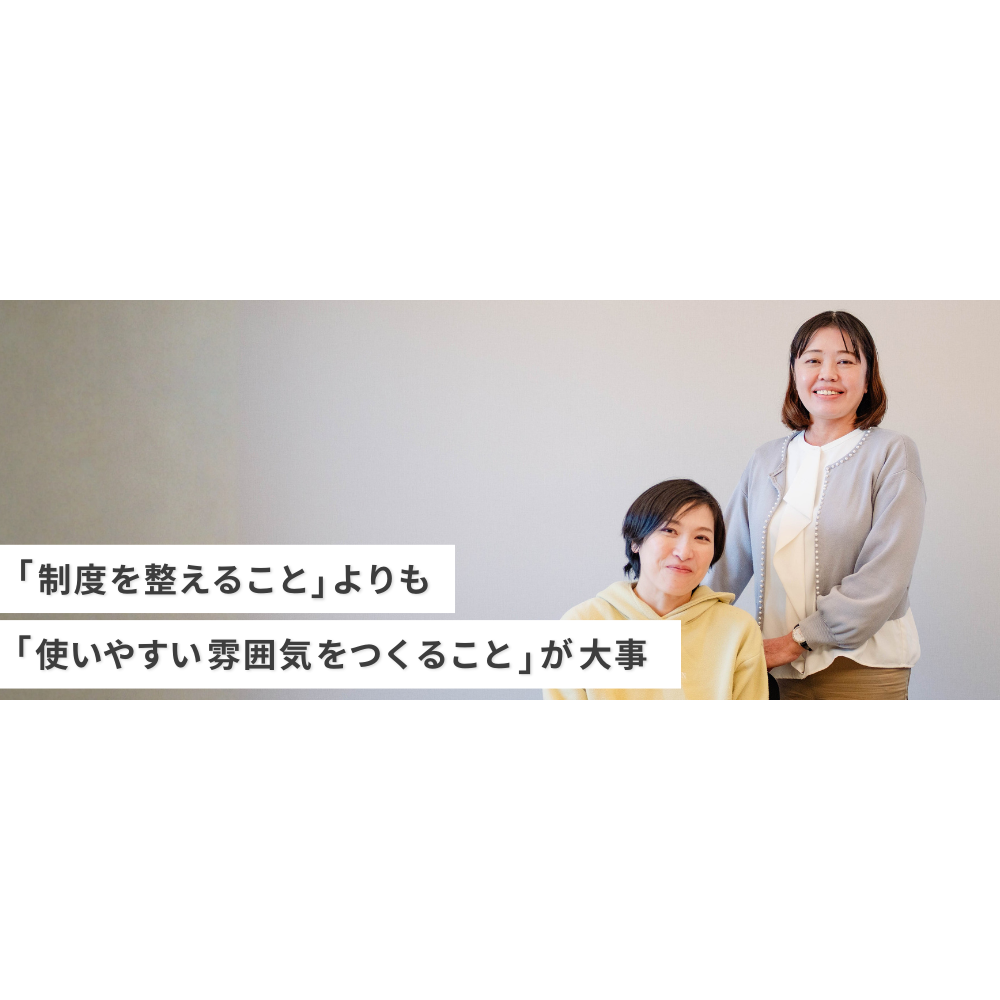スマートフォンアプリの開発に洗濯代行サービス、電気自動車のカーシェア。これらの事業を全て1社で手掛けている企業をご存じでしょうか。
新興のIT企業を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、正解は出光興産。2019年、昭和シェル石油と「世紀の大再編」を経て新たなスタートを踏み出した同社は、「石油」事業にとどまらない新たな挑戦を次々と打ち出しています。
創業から110年の歴史を持つ老舗企業に今、一体何が起きているのでしょうか。今回は事業変革プロジェクトを担い、変化の真っただ中に身を置く鶴岡智之さんと尾上香奈子さんの2人にお話を伺いました。資産を生かし、時代に合わせて事業を作り続ける──長い歴史の中でアップデートを続けてきた、出光興産の哲学に迫ります。
<記事の見どころ>
●社内に新規事業の部署が4つ! 2050年を見据えた事業づくりを本気でやる証左
●洗車アプリからEVのカーシェアまで──石油会社「らしくない」プロジェクト
●6兆円企業を支える製油所のデジタル変革、まずは数百億円かかる保全業務にメス
●エンジニア出身からMBAホルダーまで。多様な人材が新規事業開発に関わる
●カラーが違う2社が融合したからこそ、多様性を認める社風になった
●「老舗企業にいながら新規事業を作る」面白さ。資産を生かし、時代に合わせたサービスを作り続ける
●創業から引き継がれる「社会貢献」と「事業を通じて人を育てること」への思い。次の100年づくりに欠かせないこと
社内に新規事業の部署が4つ! 2050年を見据えた事業づくりを本気でやる証左
──本日はよろしくお願いします。鶴岡さんと尾上さん、お二方とも新規事業にまつわる部署にいらっしゃると聞きました。どのような仕事をしているのか、教えていただけますか。
鶴岡:私は2020年1月に設立した「デジタル変革室」で企画課長を務めています。この部署は業務のデジタル化やいわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション)を全社で進めるために生まれた組織です。部署横断、バリューチェーンの連携を切り口にプロジェクトを10個ほど進めながら、デジタル化に向けた社員の意識改革も並行して行っていくのが、大きなミッションです。

鶴岡 智之(つるおか ともゆき):2004年 出光興産株式会社に入社。生産技術センターや製造技術部など主に技術系の部署でキャリアを重ね、2015年から経営企画部に。グループ全体の投資企画・管理に関する業務に従事する。経営の基礎を「実務」を通じて修得しながら、一般的な学問としての経営学を学びたいと、技術経営系大学院を修了。2019年の経営統合では投資戦略の策定や投資の意思決定の仕組みなど、両社にまたがる業務を経験。2020年1月より現職。
尾上:私が所属している「販売部ビジネスデザインセンター」は既存の販売ネットワークを活用した新たなサービスや商材の開発に取り組む部署として、2019年10月に生まれました。市場探求を起点とした新規ビジネスを考えるのがミッションで、最近ではスマートフォンで洗車のオーダーができるアプリ「AND WASH」や複合型ランドリー施設「WASH TERRACE」などの立ち上げプロジェクトに携わっていました。
──デジタル変革室とビジネスデザインセンターですか。新規事業を考える部署が、社内にいくつもあるんですね。
鶴岡:はい。この他にも地域創生など社会ニーズへの対応を切り口とする「Next事業室」や、出光が持つ先端技術をベースとした新事業を考える「技術戦略室」もありますよ。

──そんなにあるんですか! なぜ、そこまで新規事業に注力しているのでしょう。
鶴岡:足元では新型コロナウイルスの影響があるものの、感染拡大が収束してから数年の間は、経済の発展を背景にグローバルでの石油需要は増え続けるでしょう。しかし、それが続けば同時に地球環境へ大きな負荷をかけてしまいます。
中期経営計画でも発表しましたが、私たちは世界全体で環境問題への対策が進み、2030年をピークに石油の需要が落ちていくと想定して、これからの事業を作っていこうとしています。30年後まで見据え、どのような未来が来ても対応できる企業になるため、あらゆる側面から事業の可能性を検討しているというわけです。
尾上:特に日本においては、人口減少や電気自動車(EV)の普及などで10年後には石油需要が3割減ると想定しています。実際、サービスステーションはガソリンの需要低下などを背景に店舗が減り続けています。1994年度の6万421店舗をピークに、2019年3月には2万9,000店舗を切るところまできました。この30年でほぼ半減です。
このままだとお客さまとの大切なタッチポイントも、長年お付き合いしてきた特販店(特約販売店)の皆さまとのネットワークも失ってしまう。それを食い止め、逆に新しいお客さまとの接点を創出していこう、ということで、例えば最近では、洗濯代行サービスを行うランドリーの複合店舗をサービスステーション跡地に作るなど、既存ネットワークを活用しながら、新たな生活サービスを提供できるよう事業開発およびその実証を行っています。

尾上 香奈子(おのうえ かなこ):2009年 昭和シェル石油株式会社に入社。流通業務部基地管理センターに配属され3年間、国内の製造と販売をつなぐ業務に従事する。法学部出身の経歴を生かし、2012年に法務部へ異動。経営の知識を得たいと、社内公募に手を挙げ、2017年8月よりスペインのESADE Business Schoolに留学しMBA取得。帰国後、2019年4月よりリテールマーケティング部新規プロジェクト課(現、販売部ビジネスデザインセンター)に所属。
洗車アプリからEVのカーシェアまで──石油会社「らしくない」プロジェクト
──尾上さんが携わった洗車アプリAND WASHは、どのような経緯で開発されたのですか。
尾上:このアプリはスマートフォン上で洗車の設定から決済までを行えるサービスで、ユーザーはETCのような感覚で洗車ができます。
もともとアプリありきで始まったプロジェクトではないのですが、洗車する人にヒアリングをした際に、「メニューに使われている言葉が分かりにくい」「その都度車から降りるのが面倒」などさまざまな不満があることが分かりました。その不満を解消するツールがこのAND WASHアプリです。
他にも「撥水(はっすい)ポリマー」という単語を「ピカピカが長持ち」という説明に変えるだけでも、利用のハードルは下がります。サービスの内容が固まったら半年ほどでアプリ開発を終え、2020年4月に実証実験を開始しました。

──面白いですね。どんなメンバーで開発を進めたのでしょう?
尾上:販売部ビジネスデザインセンターは、基本的に2〜4人1組のチームで動きます。マネジャーがプロジェクトごとにそれぞれ違った経験や専門性を持つメンバーをアサインするんです。
アプリ開発の技術者やサービスステーションでの営業経験が長いメンバー、別の会社で新規事業を担当してきた方など、多様なメンバーとそれぞれの経験や強みを生かしながらプロジェクトを進めるのは、学ぶことも多く、本当に楽しいですよ。
──AND WASH以外のプロジェクトもぜひ教えてください。
尾上:他チームのプロジェクトですが、電気自動車のカーシェアリングサービス事業「オートシェア」を展開しています。2019年8月には岐阜県飛騨市・高山市、2020年5月には千葉県館山市のサービスステーションを通じ、超小型EV「ジャイアン」を貸し出しています。
太陽光エネルギーを用いて、非接触型の充電を行うといった最新技術も使っていますし、社内のさまざまな部署を横断するだけでなく、社外の特販店さんなど、多くの人を巻き込む目玉のプロジェクトです。ゆくゆくは公共交通機関が乏しい地方での実用化やMaaS(Mobility as a Service)構築の一助とすることを目指しています。
6兆円企業を支える製油所のデジタル変革、まずは数百億円かかる保全業務にメス
──鶴岡さんのデジタル変革室では、どのようなプロジェクトを進めているのでしょうか。
鶴岡:最も力を入れているのは製造の根幹を担う事業所(製油所を含む)のDXプロジェクトです。事業所は原油から石油製品や石油化学製品を精製するまさに「会社の心臓部」ともいえる施設ですが、50年ほど操業を続けていることもあり、メンテナンスに多大なコストが要するのが大きな課題となっていました。
事業所1つで東京ディズニーランド7.5個分の面積があるのですが、これが全国にいくつもあり、これらの現場を守るために、年間で数百億円かかるんですよ。
──そんなにかかるんですか……!
鶴岡:しかも、こうしたメンテナンスはエンジニアたちの「匠の技」によって守られているのですが、彼らは忙しすぎて新たな施策を考えるような時間も取りにくい。そういった時間を創出するため、仕事の進め方を根本から見直すことを目的とし、その手段としてデジタルを活用しようというプロジェクトです。
まずは現場を自分たちの目でしっかり観察しようと、保全を担う人たちとじっくり会話するだけでなく、彼らの仕事を後ろからずっと見て、「どのタイミングでExcelを開いたか」「どんな資料を印刷しているのか」などを徹底的に記録しました。そういう具体的な行動まで見える化し、業務のムダはないのか、事業所と議論しながらプロジェクトを進めました。
──こう言ってしまってはなんですが、デジタル化といっても地味な作業から始まるんですね。
鶴岡:そうですね。製造現場のエンジニアが当たり前だと思っていて、これまでのようなヒアリングでは出てこないような「潜在的な困りごと」を発見するのがデジタル化の第一歩だと考えています。デザインシンキング的な考え方ですね。DXを進めるにはアナログなアプローチは絶対に必要です。プロジェクトに取り組んでみて、初めてデジタルとアナログのバランスが大切だと思うようになりました。

ただ、アナログなアプローチを使うといってもスピード感は重要です。デジタル変革室の室長はブリヂストンから迎えた三枝が務めていますが、前社の取り組みを踏襲し、この事業所のDXプロジェクトでは、困りごとの抽出から対策案の実地検証まで約100日で進める「100日スプリント」を採用しました。
実地検証を終えた100日後の現在、実際にデジタル化にチャレンジしていく段階に入りましたが、そのやり方としても「やりながら最適なものに仕上げていく」、いわゆるアジャイル開発にて事業所と二人三脚で案件を推進しています。足元で注力しているのは、何度も繰り返し行っていた作業を一本化する取り組みで、年間数百時間の作業時間の削減、それに伴う年間数十億円以上のメンテナンス費用の圧縮を期待しています。
エンジニア出身からMBAホルダーまで。多様な人材が新規事業開発に関わる
──ありがとうございます。ここまでお話しいただいた新規事業はどのようなメンバーが進めているのでしょう。鶴岡さんも尾上さんも、どのような経緯で今の部署に入ったんですか?
鶴岡:私は2004年入社ですが、大学で化学工学を専攻していたこともあり、最初はエンジニアリング領域の部署を希望し、生産技術センターや製造技術部にいました。入社して数年後、運良く事業所内の大型装置の建設プロジェクトに参画でき、プロセス設計、建設、運転まで一連の業務に携わり、技術者としての醍醐味(だいごみ)を経験させてもらいました。
その後、2015年に経営企画部へと異動しました。会社全体の投資戦略を策定したり、投資の意思決定の仕組みを構築したり。一方で、このような経営企画の実務をこなしながら、一般的な経営学とのつながりを学びたいという気持ちが高まり、2年ほど夜間/休日の技術経営系大学院に通いました。
デジタル変革室は希望していたわけではなかったので、異動を聞いたときはびっくりしましたが、全社のDXを推進するだけでなく、そのための組織、文化を作っていくことを考えると、経営企画で得られた全社とつながりがある点は有利に働いていると思います。

尾上:私は2009年に昭和シェルへ入社して、3年間、流通業務を束ねる国内物流の部署にいました。流通業務は販売部門と製造・供給部門の板挟みになるところで、この調整の難しさに疑問を持ち、企業全体を俯瞰(ふかん)した課題に興味が湧いたんです。
その後法務部へ異動し、コーポレートガバナンス体制を作るような仕事をしました。会社が統合するときの組織のガバナンスを担当するなど、勉強にもなって楽しかったのですが、だんだんとビジネスのサポートではなく、自分自身がビジネスをやってみたいという気持ちが大きくなりました。そのタイミングで、社内制度を使ってスペインのビジネススクールに留学し、MBAを取得したんです。
会社が変わる中で、新しい取り組みを模索したいと考えていたため、留学先はアントレやイノベーション系に強い学校を選びました。帰国後に今の部署に配属になりましたが、これまでの経験やMBAで学んだことが生かせる環境だと思っています。
──お二人のキャリアを聞いていると、多様な経験を生かして新規事業を進めているという印象を受けます。そうなると、若手が活躍するのが難しい面はありませんか? 例えば、新卒でも声を上げれば入れるチャンスはあるのでしょうか。
尾上:ビジネスデザインセンターはメンバーの年齢構成がバラバラで、20代の若手社員もプロジェクトリーダーとして活躍しています。
できたばかりの部署なので、新入社員が配属された前例はまだありませんが、新しいものをどんどん取り込む柔軟な感性や、専門的なデジタルスキルに対するニーズは高いので、そういうものを持っている人が即戦力として来てくれたら個人的にはうれしいです。キャリアチャレンジ制度という新しい取り組みも始まっていますし、チャレンジしたいと手を上げれば尊重してくれる風土があります。
鶴岡:1月の立ち上げ時は4人で始まったデジタル変革室ですが、今は17人ほどの部署になりました。30歳前後の社員が活躍している印象です。DXを推進するためには、データサイエンティストやデザイナーといった社内で補えないスキルも必要なので、社外のエキスパートも採用しています。その下で勉強しながらスキルを磨く、というスタンスで積極的に若手を取り入れていきたいと考えています。
先日、完全オンラインで開催した夏のインターンシップでは、学生にアドバイスをするという立場で経営企画部のメンバーも参加しましたが、逆に学生の皆さんからもらった意見がとても参考になりました。会社の枠にハマっていない感性から学ぶことは多々あります。2000年以降に生まれたZ世代が、新卒で入社してくるこれからに大いに期待しています。
カラーが違う2社が融合したからこそ、多様性を認める社風になった
──新規事業の立ち上げに関わる人もそうですが、出光興産で活躍している人材はどのような特徴があると思いますか?
尾上:分かりやすい人物像を示せればいいのですが、こういう人は活躍できるとか、この人は合わないとかっていう考え方はあまりないんですよね。
事業領域が広いので、理系出身でも製造や研究開発だけでなく営業や事業企画で活躍できる場合もありますし、海外勤務もあり得ます。皆さんそれぞれ自分の個性を生かして活躍できます。私としては、カラーが違う2社が融合した会社だからこそ、そういう排他的な概念を作りたくないという思いもあります。

──その点もお伺いしようと思っていました。2社が統合した今の出光の社風ってどのようなものなのでしょうか。
尾上:今まさに社風が作られている最中かと思います。個人的には「意思を持った個人が、自分らしい個性を発揮できる組織」といった感じで、こうあるべきという固定観念がなく、事務、技術いずれの系統コースに関わらず、その人の経験と個性という資産を武器にして働ける会社にしたいと思っています。
鶴岡:これからの会社を作っていくためには、「多様性」が一つのキーワードになると考えています。多種多様な人材が集まって融合していくだけでなく、社員一人ひとりが異なる人々や文化に触れることで、自らの内に多様性を育んでいく。それは当人にも会社にとっても幸せなことで、新たな事業構造の構築につながるものだと信じています。
尾上:文化が違って意見が食い違うことがあっても、共通する部分もたくさんあります。ガチガチに固められた「求める人材像」に合わないと感じた人に、疎外感を与える環境を作ってもメリットはありませんから。違いを認めずに排他的になるより、多様性に目を向けていた方が楽しいですよね。
「老舗企業にいながら新規事業を作る」面白さ。資産を生かし、時代に合わせたサービスを作り続ける
──お二人から見て、新卒で今の出光興産に入る面白さやメリットはどこにあると思いますか?
尾上:ちょっと古臭いかもしれませんが、老舗企業にいながら新規事業を作るって、面白さがありませんか?
今ちまたで持てはやされる企業は既に「カッコいい」が出来上がっているわけですが、われわれは古いものを生かして「カッコいい」を作る。状況をマイナスからプラスに持っていった経験と実力があれば、正直、どこでも活躍できるでしょう。
鶴岡:経営統合や新型コロナという大きな動きは、これまでのあり方を大きく変えるチャンスだと捉えています。事業のスケールも大きいので、自分の提案が社会につながっていると実感できるのもあると思いますね。
尾上:約100年の時間をかけて会社が守ってきた全国に点在する基盤の上に、時代に合わせたサービスを乗せて新たな価値を作っていけるのは、歴史のある企業で働く醍醐味(だいごみ)だと思います。
一見、古く見えるものの中から新たなビジネスの芽を育てる経験ができる。さらにそれを歴史的知見と大きなリソースを持った会社がバックアップしてくれる、ダイナミックな環境があります。
──新卒で入社した場合、どのようなキャリアを歩むことになるのでしょう。
鶴岡:先ほど尾上がお話しした通り、出光にはこうあるべきという固定観念がないので、自由なキャリアパスを描ける会社だと思います。
製造業の企業ということもあり、入社後に理系は技術系、文系は事務系の道を歩むイメージがあるかもしれませんが、私のようにエンジニアから経営企画に動いた実績もありますし、尾上のように現場で経験を積んだ上で、大学に通うこともできます。人それぞれの個性とやる気を尊重しながら、人を育てようという気概があるんですよね。
創業から引き継がれる「社会貢献」と「事業を通じて人を育てること」への思い。次の100年づくりに欠かせないこと

2020年12月に予定する、移転直前の東京・大手町新オフィス31階にて撮影
──歴史の話が出ましたが、出光は採用コンセプトに「NEXT BREAKTHROUGH」を掲げており、果敢に挑戦を続けてきた約110年の歴史をベースに、今後もその姿勢は変わらないと打ち出されています。変化の激しい時代でも、長く生き残る会社にはどんな特徴があると考えますか?
鶴岡:私が入社した2004年の話なんですけど、当時社長であった天坊(創業後長らく非上場だった当社株式を2006年に上場)が入社式のスピーチで、「現状維持は退化。大切なものは残しつつ、変えるべきものはどんどん変えていこう」と話しをされました。この言葉が今でも心に残っています。
今は新型コロナの影響もあって、出光も含めて世界的に危機的な状況といえるでしょう。ただ、110年もやっていれば、諸先輩方も同じような境遇に向き合ったと思うんです。歴史を濃密に観察して考察すれば、きっと今の状況にも反映できるはず。110年続く事実を培った歴史こそ、学びの宝庫だと考えています。
今私が大切にしたいのは、歴史からの学びを大切にして、変えるべきものは変えていくという思い。時代や流行のフレームワークは変わっても、最終的には社会を通じて「練習」を重ねて、進み続けるだけです。社会の変化に対応して、ビジネスをいろんな切り口から実験した軌跡に答えが浮かび上がるのでしょう。
──挑戦を続けることで道が開けると。確かに創業者の出光佐三氏も創業間もないころから、中国へ事業を展開するなど、「挑戦」にまつわるエピソードは多いですね。
尾上:そうですね。これまでの110年、そしてこれからの100年先も、残していきたい価値観は変わりません。創業から続く「社会貢献」への強い気持ちが、個々に浸透しているのが出光の強さだと思います。また、「人間尊重」から受け継がれる「事業を通じて人を育てること」を重んじる風土。社会環境が移ろいゆく中でも変わらないコアバリューは、これからも挑戦を続けていく上で欠かせないものです。
──今年は新型コロナウイルスの影響もあり、就職活動に不安を抱く学生も少なくありません。これから就活を本格化させる学生に向けて、メッセージをお願いできればと思います。
尾上:これからの時代、働くことを通して自分は何を実現したいのか、を考えながら自立的にキャリアを積み上げる意識が大切になるかと思います。その中で、当社は日々いろいろな力を蓄えられるような経験ができる場を多種多様に提供している会社だと思うので、ぜひ選んでくれたらうれしいです。
鶴岡:ぜひこの状況をチャンスと捉えてほしいと思います。パンデミックでフィジカルな接触が制限される一方、デジタル領域などでは選択肢が増えているのも事実。これを乗り越えて社会を元気にできたと実感する日のために、普段できないチャレンジをするのもいいと思います。ぜひ、私たちと一緒に社会を元気にしていきましょう。
▼企業ページはこちら
出光興産
【ライター:鳥山愛恵/撮影:百瀬浩三郎】