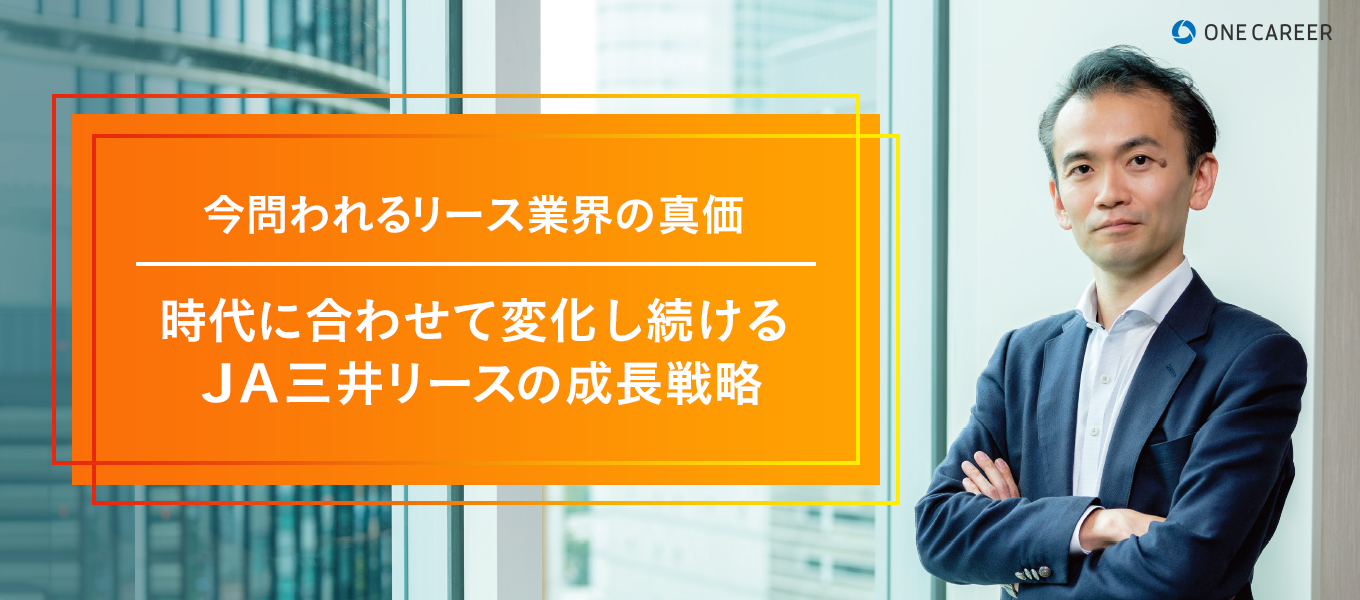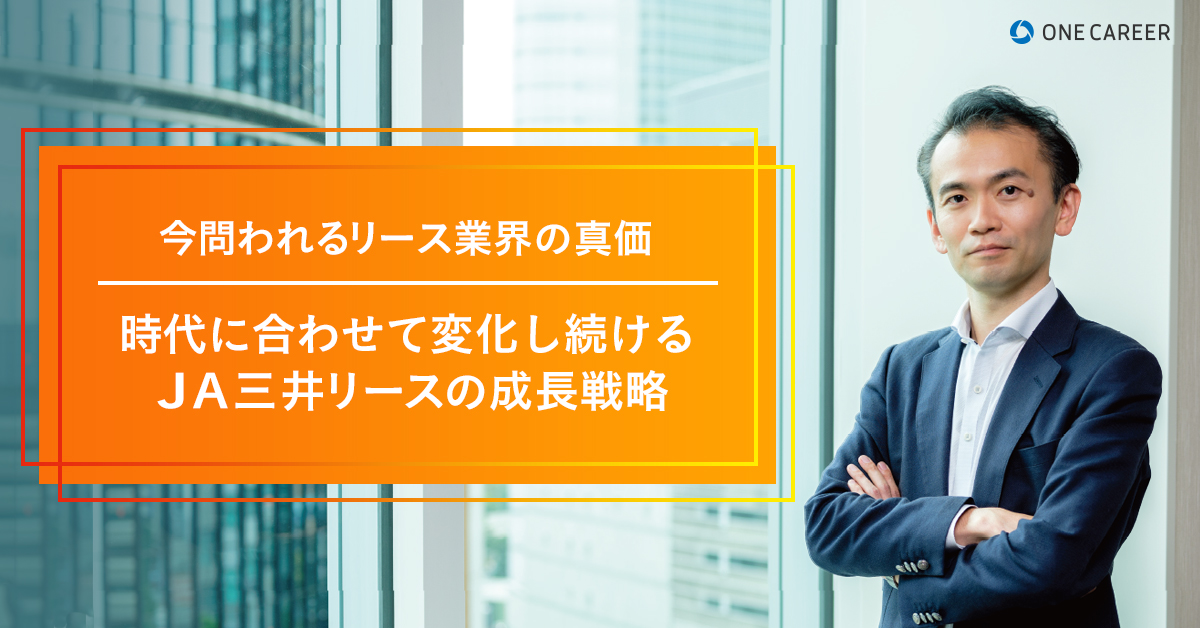「私はこの会社で長く勤めてきましたが、これほどまで仕事の幅が広がっていることに本当に驚いています」
長い歴史を持つ企業の多くは、市場環境の変化に適応し、生き残りと発展を図るべく、コア事業を転換させてきました。
「冬の時代」を乗り越えるために事業投資を行うようになった総合商社、写真フィルム市場の縮小を受け、ヘルスケア事業に舵(かじ)を切った富士フイルムなどがその代表例と言えるでしょう。
市場変化の波にさらされているのは、金融業界も例外ではありません。JA三井リースも事業転換を行う企業の1社です。リース会計基準の変更により業界のルールは激変。国内のリース取扱高は縮小傾向にあります。
しかし、同社の人材開発室長である木村氏は、苦境に見えるこの状況に対し、「むしろ、『お客さまにとっての本質的な価値とは何か』『お客さまのために当社ができることは何なのか』をあらためて考えるようになった」と話します。
挑戦を続ける同社に、ワンキャリ編集部が迫りました。
会計基準変更で市場のルールが変化。リース業界の「苦境」と「可能性」

木村充寛(きむら みつひろ):JA三井リース株式会社 人事総務部 人材開発室長。1996年に旧協同リース株式会社へ入社。名古屋支店、大阪支店、経営企画室などを経て、2015年7月より人材開発室。
──木村さんは、営業、経営企画、人材開発とさまざまな部署で経験を積まれ、長年にわたってリース業界を見てこられました。そんな木村さんから見て、リース業界は現在どのような状況にあるのかを教えていただきたいと思います。その前に、まずはリースがどういうビジネスなのか、簡単にご説明いただけますか?
木村:簡単に言えば、リースとはモノを購入してお客さまに貸すというビジネスです。「貸す」と言ってもレンタルとは違い、リース会社は在庫を持ちません。リース会社が機械やPCなどを、お客さまが必要になったときにその都度購入して、5年、10年など年単位で長期間お貸しします。お客さまには、月々のリース料をお支払いいただきながら使用してもらいます。お客さまはリースで借りたモノを、自社で購入するのと同じように使うことができるのです。リースではモノの調達にまとまった資金をかけずに済むため、キャッシュフローを改善できたり、銀行の借入枠を温存できたりするというメリットがあります。要するに、リースは「モノを通したファイナンス」なのです。
──2008年4月にリース会計基準が変更され、リース業界に大きなインパクトを与えたと聞いています。この会計基準変更と、業界の変化について詳しく教えてください。
木村:業界の売上は現在堅調ですが、リース取扱高は全体的に縮小傾向にあります。リースの市場規模は、会計基準変更直前の2007年には約7兆円でしたが、2018年には約5兆円に縮小しています。以前は、リース取引はバランスシート(B/S)(※)に記載する必要がなく、リースには決算書の見栄えを良くできるというメリットがありました。しかし、会計基準変更で取引をB/Sに記載することが義務付けられ、そのメリットが薄れてしまったのです。
(※)バランスシート(B/S)……貸借対照表。財務三表の一つ。企業の資産や負債といった財務状況を表すもの。
──これまでリースはB/Sを軽くする手法として使われてきたが、会計基準変更によって以前ほど用いられなくなってきたと。業界のルール変化によって、リース業界は苦境に置かれたのではないですか?
木村:確かに会計基準変更のインパクトは大きかったですが、むしろ「お客さまにとっての本質的な価値とは何か」「お客さまのために当社ができることは何なのか」をあらためて考える機会になりました。会計基準変更は、業界がリースの提供価値について考え直し、リース以外も含めた多角的なサービスを提供する転換点になったのです。
──リース以外の金融サービスも提供しているとは意外です。
木村:リース会社は銀行法のような規制に縛られていませんから、リースにとらわれず多様なソリューションを提供できるのです。リース会社はこれまでもお客さまのニーズに合わせて事業範囲を拡大させてきましたが、これからもいかに時代に合ったビジネスを創出できるかが成長のカギとなります。
例えば、お客様とパートナーシップを組んだ新規事業創出。私たちはさまざまな業界の企業と取引があり、強固な顧客基盤を築いています。その関係性を生かしてパートナーと共同で新規事業を創出することもあるのです。
成長著しい海外市場へ。提携やM&Aも駆使した積極的な海外進出

──リース業界が転換点を迎える中、JA三井リースはどのような事業戦略を採っているのでしょうか?
木村:リース業界も変化が迫られていますが、リースというのはお客さまあってのビジネスです。お客さまの事業が変われば、当然そのニーズやわれわれが注力すべき分野も変わっていきます。当社が今注力すべき事業だと捉えているのは、海外・ICT・食農の3つです。
まず海外事業ですが、日本では取扱高が減少し始めたリースも、海外では未開拓の市場が広がっています。リース業界全体で見ると、海外事業の市場規模は2012年から2018年にかけて、約5,000億円から約1兆5,000億円と、約3倍の伸びを見せています。各社は海外企業とリース契約を結んだり、日本企業の海外進出のサポートをしており、JA三井リースも、今後さらに海外事業を強化していきます。
当社が特に積極的に進出しているのは、成長著しく需要も大きいアジア市場。台湾の半導体・シンガポールの船舶・インドネシアの鉱山などに関連する企業にリースや投資を行っているほか、特にインドネシアでは個人向けに自動車のファイナンスも行っており、現地に密着した産業として大きな役割を担っています。
──海外拠点を作るほか、パートナー企業と連携することもあるのですか?
木村:はい。 2019年6月に、アメリカのリース会社First Financialグループを完全子会社化することが決まりました。他にも、日系企業の海外進出支援などの実績があります。これからは外部パートナーとの連携を通じて、海外事業を多角化させていくつもりです。
──海外事業の強化には、多数のグローバル人材が必要だと思います。社内ではどのように人材育成を行っているのですか?
木村:グローバル人材育成施策として、オンライン英会話や講師派遣型講座など、希望者にはさまざまな英会話スクールを用意しています。加えて、インドネシア語は、現地の大学で1年間学んでもらう研修員制度があります。業務研修としては、当社現地法人への派遣もありますし、若手向けに海外企業で1カ月間経験を積むインターンシップも用意しています。これからの時代、海外赴任は当たり前になり、特別なことではなくなるでしょう。国内事業しか経験したことのない社員も海外に行くことになると思いますし、もしかしたら、来年は私が海外にいるかもしれません(笑)。
国内では成長産業であるICT領域・使命感を持つ食農領域に注力

──海外市場は成長していても、市場が伸びていない国内事業は正直なところ厳しいのではないでしょうか?
木村:いえ、そうではありません。リースという手法にとらわれずに、お客さまにとってより価値の高いサービスを提供し、さらなる成長を目指しています。
国内では、急速に伸びているICT関連事業への対応を進めています。パートナーとなるのは大きな企業から、ベンチャーまでさまざま。彼らとの連携を強めるため、設備投資の支援や資金面のサポートを行っています。例えば、建設現場と職人をつなぐマッチングアプリ「助太刀」の運営会社、国内や東南アジアで通信設備を提供する「JTOWER」などへの出資があります。
──JA三井リースがすでに強みを持っている食農領域はいかがでしょうか?
木村:私たちはJAの看板を背負っていますから、日本の農業を支えることに強い使命感を持っています。市場の変化に合わせて、農業も変わっていきますし、私たちはそのサポートをしていきます。
2019年4月には、第1次・第2次・第3次産業をつないでいくなど、農林水産業や各関連ビジネスの枠組み作り・新たな事業領域の開発のために「食農ビジネス推進部」を新しく立ち上げました。リース事業で培ったネットワークを活用し、JAグループ、三井グループ、そして私たちのお客さまのマッチングプラットフォーム構築を目指しています。例えば、優れた農業系の技術を持つスタートアップ企業でも、農家とつながりがないために商品を売り込めないということがよくあるのですが、私たちが両者の間に入ることでWin-Winの関係を築けます。全国のお客さまにサービスを提供するため、食農業界最大のプラットフォーマーを目指しているのです。
──海外進出、ベンチャー投資、マッチングプラットフォーム……。リース会社のビジネスが大きく変わりつつあることがよく分かりました。
木村:これからも、お客さまのビジネスの変化に合わせて変化し続けていきます。
私はこの会社で長く勤めてきましたが、これほどまで仕事の幅が広がっていることに本当に驚いています。事業領域が広がりつつあるJA三井リースに今入社すれば、大きな変化に立ち会えると思いますよ。
スキルだけでは不十分。金融に求められるのは信頼関係を築く「人間力」
 ──木村さんご自身は、どのようなキャリアを歩んできたのでしょうか?
──木村さんご自身は、どのようなキャリアを歩んできたのでしょうか?
木村:私は1996年に入社しました。名古屋や大阪で営業部門を計15年、東京本社で経営企画部を3年経験したのち、2015年7月から人材開発室に所属しています。
2008年、旧2社が合併した時は経営企画室にいました。別々の会社を一つにまとめるというのは、事業にとっても社員にとっても非常にインパクトの大きい仕事です。
その後、大阪支店に移って京都の農家向けファイナンスに携わりました。印象深かったのは新規で就農するイチゴ農家さんに、設備投資のサポートをしたときですね。就農したばかりの農家は、多額の融資を受けにくいのが一般的です。支援からしばらくしてその農家さんを訪れた際、「あの時は本当にありがとう」と感謝され、心の底からうれしかったことを今でも覚えています。これぞ商売の醍醐味ですよ。
正直に言えば、この取引の規模はそんなに大きなものではありません。しかし、経営企画の経験を通じ、農家への支援が全社的に重要な仕事だと再認識できたからこそ、大きなやりがいを感じられたのだと思います。こうした取り組みを続けることで、日本の農業は強くなるはず。その一端を担えることを誇りに思っています。
──さまざまな仕事を通じて目線が上がっていったということですね。新卒社員は、入社後にジョブローテーションでさまざまな部署を経験するのでしょうか?
木村:はい。基本的には、最初の10年間で3つの部署を回ります。人にもよりますが、専門営業部・エリア営業部・機能部門・海外現地法人など、さまざまな部署でキャリアを積んでいきます。
──JA三井リースは社員をじっくり育てていくというスタンスだと思います。育成に時間をかけるのはなぜでしょうか?
木村:商材を持たない金融ビジネスでは、「人間力」が求められるからです。リース契約は期間が長いですし、一度契約いただくとお客さまとは長くお付き合いすることになります。また、お客さま同士をつなぐプラットフォームになるにも、各地の事業者の方の信頼を獲得し、その情報に精通することが不可欠でしょう。金融の第一線で活躍するためには、スキルはもちろんのこと、時間をかけてさまざまな知識や経験を積むことが大事なのです。
──ビジネスモデル上、短期的に商品を売り込むようなスキルだけでなく、長期的に信頼関係を築くための「人間力」も大事であるということですね。しかし、「若手は活躍できないのでは?」という疑問を抱く学生もいそうですが、これについてはいかがでしょうか。
木村:もちろん、若手が大きなプロジェクトの一部を担うようなチャンスはありますよ。新卒社員には将来のリーダーに育ってほしいからこそ、若手のうちに経験を積む機会を用意しているのです。一方で、先ほどお話ししたような理由で、簡単にリーダーになれるわけではないという点も事実です。
また、今後は若手社員が海外研修を受けたり、新規事業に携わったりする機会が増えてくるでしょう。例えば、先ほどもお話ししたインドネシアの研修や海外インターンは2年目から応募できますし、実際に現地に赴任している若手社員もいます。
「長期的なキャリア形成=若手は意見を言えない」ではない。新しい時代に求められるのは自分の意見を持つ人材
 ──JA三井リースではどのような人材が活躍できるのでしょう?
──JA三井リースではどのような人材が活躍できるのでしょう?
木村:自分の意見を主張できる人材ですね。間違っても構わないので、自分でしっかり考えた上で「私はこう思います」と臆さずに言える人に来てほしいです。事業が変化していく中、ベテラン社員にはない若手の視点から意見を出してくれることを期待しています。
そして、地道な努力ができることも重要だと思います。金融には売れ筋の商品などはなく、個々のお客さまのニーズに合わせてソリューションを提供しますから、日々お客さまの話に耳を傾ける姿勢は欠かせません。「JA」「三井」という大手の看板に安住せずにコツコツと努力し、キャリアを積み上げていけるような学生には合っていると思います。
──最後に、この記事の読者に向けてメッセージをお願いします。
木村:先ほど話した通り、リース会社は商材を持ちませんから、社員の人間力が差別化につながります。だからこそ、JA三井リースは社員一人一人の個性を大切にしている会社なのです。
そして、JA三井リースはこれからも、お客さまとともにビジネスを変化させていきます。新しい時代に活躍する企業を支え、ともにビジネスを作り上げていきたいという志を持った学生の皆さんにぜひ来てほしいと思っています。
▼企業ページはこちら
JA三井リース株式会社
【ライター:大澤美恵、YOSCA/編集:辻竜太郎/カメラマン:塩川雄也】