
企業情報
| 会社名 | 株式会社 毎日新聞社 |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 設立日 | 1872年(明治5年)2月21日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 丸山 昌宏 |
| 所在地 | 〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 |
| 資本金 | 41億5000万円 |
| 従業員数 | 2,600人 |
| 事業内容 | 日刊新聞の発行、雑誌や書籍の発行、デジタルメディア事業の展開、スポーツや文化事業の企画開催、その他各種の事業 |

突然ですが、皆さんは日々どのようにニュースに触れていますか?
いまは「新聞」よりも「インターネット」が多いのではないでしょうか。ネットに親しんでいる皆さんにとって、「新聞」や「新聞社」は馴染みの薄いものかもしれません。しかし、ネットニュースには毎日新聞をはじめとする報道機関の記者たちの、ねばり強く、地道な取材活動の積み重ねによって配信されているものもあります。「新聞社」は皆さんにとって実は身近な存在なのです。
一方で、皆さんが「働く」ことを考えたとき、記者がどのように取材しているのか、どれだけの人の手を経て皆さんに新聞が届くのか…など、「新聞社の仕事」については、知らないことが多いのではないでしょうか。
そこで、新聞社が担う社会的な使命や働く人が感じているやりがいなど、さまざまな形でお伝えしたいと思い、毎日新聞社のインターンシップ「毎日メディア塾」を開校しました。
新聞社の仕事は、決して記者職だけではありません。新聞を読みやすく、わかりやすくするデザイナーや安定的な財源を確保することで毎日ジャーナリズムを守るビジネス部門、そして新しいビジネスを生み出す技術を開発するITエンジニアなど様々な仕事あり、社員全員が報道の使命を担っています。
皆さんが勉強していること、将来やりたいと思っている仕事が新聞社には必ずあります。
皆さんのご応募を心よりお待ちしております!
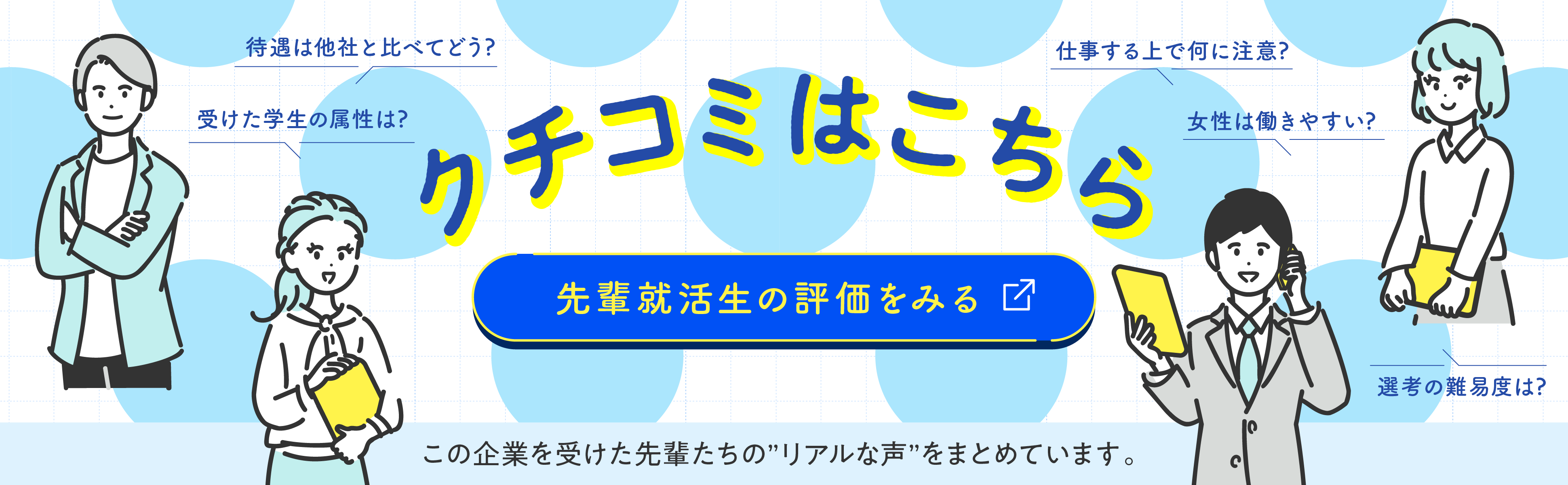
| 会社名 | 株式会社 毎日新聞社 |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 設立日 | 1872年(明治5年)2月21日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 丸山 昌宏 |
| 所在地 | 〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 |
| 資本金 | 41億5000万円 |
| 従業員数 | 2,600人 |
| 事業内容 | 日刊新聞の発行、雑誌や書籍の発行、デジタルメディア事業の展開、スポーツや文化事業の企画開催、その他各種の事業 |

毎日新聞社は150年近く前から新聞を発行し続けています。現存する日刊紙では、最も歴史ある新聞社です。明治、大正、昭和、平成、そして令和と、常に時代の最先端に立ち、事実を伝え続けてきました。
私たちは読者とともに歩んできた歴史を大切にする一方で、力強く新たな挑戦もしています。その先頭に立っているのが若手社員です。毎日新聞社はマスコミ業界のグランプリともいえる新聞協会賞を業界最多の30回受賞しています。昨年度は仙台支局の若手記者が端緒をつかみ、全国の支局で活躍している若手達が力を合わせたキャンペーン報道「旧優生保護法を問う」が選ばれました。また、2019年3月には、世界規模で若者に人気の高まっているeスポーツにおいて、高校生のための初の全国大会を開催しました。この大会も若手社員の発案から始まった、まったく新しい事業です。
若手の意見を尊重し、発案が結実するように先輩やベテランの社員が応援する。毎日新聞社は歴史があるのに、新しく変革を続ける会社です。

若手が活躍している背景には、毎日新聞社の中に脈々と受け継がれる自由な社風があります。「まだ若手だからこんなこと言っちゃだめかな」「若いのに出過ぎたことはできないかな」などと思っている社員はいません。しなくてはならないこと、すべきことは確かにあります。でも、それが終われば、自由な発想を膨らませ、さまざまなことに取り組む社員ばかりです。
会社によっては与えられた仕事を粛々とこなすことを評価するところもあるでしょう。でも、毎日新聞社は違います。社員一人一人が自分で考え、自分の足で立って歩んでいるのです。時には、その方向性がばらばらに見えることもあります。ですが、決してまとまりのない組織ではありません。組織に縛られず、個々人の発想や個性を尊重し、自由を何よりも代え難いものと社員みなが理解しているのです。

私たちは一人一人顔が違い、考え方が違い、歩んできた人生が違います。当たり前のことですが、現代社会ではとかく軽んじられがちです。白か黒か。1か0か。敵か味方か。デジタル的な考え方が社会を覆い、自由で豊なはずの時代に息苦しさを感じる人も少なからずいます。
毎日新聞社は社員の多様性だけでなく、社会の多様性も大切にしています。年齢や性差、障害の有無などのさまざまなバリアを取り除き、全ての人が生きやすく平和な社会を創ることを目指しています。このような考え方は「毎日ジャーナリズム」の実現につながっています。「報道に近道はない」を合言葉に、ねばり強い取材活動を展開し、政治・経済・外交の深層にある事実を明るみに出すスクープや困難の中にいる人たちに寄り添い救済につなげるキャンペーン、社会問題を掘り起こす独自の調査報道、分かりやすくかみくだいた解説、そして読んで役に立つ情報、コラムなどを読者に届ける――。毎日ジャーナリズムには、そんな多彩な理念が散りばめられています。
私たちが大切にしている毎日ジャーナリズムを担うのは記者だけではありません。収益を上げるビジネス部門の社員もともに担っているのです。